

【インタビューを受けた人】
株式会社やなぎ 高柳 稔様
株式会社やなぎ 吉井 沙耶様
【インタビュアー】
日本次世代企業普及機構 長谷川 颯汰
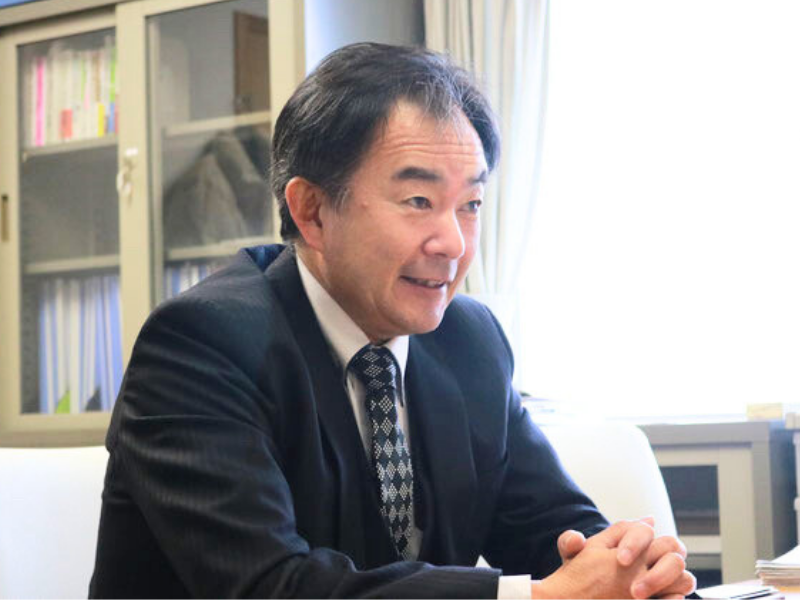

代表取締役 高柳 稔様

施行部ディレクター課 吉井 沙耶様
今回は、「人の節目に寄り添う仕事」を貫き、地域に根ざした葬儀サービスを展開されている「株式会社やなぎ」の高柳社長にインタビューをさせていただきました。
高柳社長の原体験をはじめ、葬儀という仕事にかける想い、そして「どんな人と共に働きたいか」という考えを深く掘り下げてお話を伺いました。
株式会社やなぎのポイント
・人生の節目に寄り添うサービスを展開
・人とのご縁を何より大切にする経営
・想いに寄り添い、誰かの力になれる仕事
── 長谷川:まずは、株式会社やなぎについて簡単に会社のご紹介をお願いします。
高柳社長:弊社は三重県松阪市を拠点に、葬祭事業を中心としたサービスを展開している会社です。
「人と人とのご縁を大切にする」という想いを軸に、ご家族にとって心に残るお見送りの場を提供しています。
創業以来、お葬式という場面においても、あたたかい対話と誠実な対応を大切にしてきました。地元に根ざした企業として、地域の方々からも信頼をいただいております。

株式会社やなぎの本部事務所(多気郡多気町相可1064-1)
── 長谷川:順調に成長を続けるやなぎを率いる高柳社長ですが、もともと「葬祭業を始めよう」と思われたきっかけは何だったのでしょうか?
高柳社長:実は、最初は「ブライダル事業」からスタートしていたんです。
高校卒業後は建設・土木系の業界に就職したんですが、22歳で結婚したときに、やっぱり若くて収入も少なかったので「このままで大丈夫かな?」という不安がありまして…。
そんなとき、妻の母が趣味で「お見合い写真」を預かって相手を紹介する、いわば“縁結び”のようなことをしていたんです。それを見て「これってもっと広げられるのでは?」と思ったのが最初のきっかけでした。
── 長谷川:なるほど。ご家族のご縁から、自然とビジネスのアイデアに広がっていったわけですね。
高柳社長:そうなんです。当時は「集団お見合い」なんかも流行っていて、そういったイベントを企画する中で、たくさんの方々に出会いの場を提供できたんですね。僕自身、人と接するのが好きだったので、どんどんのめり込んでいきました。
そこから、イベントで使うパーティー会場や結婚式場とのつながりが増えていって、そこで「引き出物を手伝ってもらえませんか?」「演出の部分もお願いできませんか?」といったお声がけをいただくようになりました。
正直、最初から「ブライダルで起業しよう」と思っていたわけではないんですが、気がつけばその世界に入り込んでいた、という感じですね。
── 長谷川:まさに“ご縁”が自然とキャリアを導いてくれた形だったんですね。でも、ブライダルのお仕事をされていて、そこからなぜ「葬儀」という全く異なるジャンルに踏み出すことになったのでしょうか?
高柳社長:結婚式場の方から「実はうちは葬儀もやってるんだけど、興味ないか?」と声をかけてもらったことでした。
最初は驚きましたが、実際にお話を聞いてみると、「人生の大きな節目を支える」という点では、ブライダルと葬儀って、意外と共通点があるなと感じたんです。
また当時、私たちがやっていた披露宴のサポート業務も時代の変化とともに縮小傾向で、「このままでは事業が先細りしてしまう」という危機感もありました。
そんな中で「葬儀」という新しい分野への挑戦は、ある意味で自然な流れだったのかもしれません。
そこからさらにご縁が広がって、兵庫県の葬儀社さんを紹介していただいたんです。
「やるからには一からしっかり学びたい」と思っていたので、思い切って現地に泊まり込みで修行させてもらうことにしました。

「株式会社やなぎ」設立前、やなぎ葬祭時の高柳社長と奥様のお写真
── 長谷川:本格的に学ぶ場として、兵庫県での修行に入られたんですね。初めてお葬式の現場に立たれたとき、どんなことを感じられましたか?
高柳社長:そうですね。着いたその日から、すぐにご葬儀の現場に同行することになったんですが、初日のことは今でも鮮明に覚えています。
最初に担当させていただいた故人様が、実はご遺体が損傷を受けた状態だったんですね。自害だったと思います。
当時の私は、どちらかというと「残された家族をどう支えるか」という視点で葬儀の仕事を捉えていたので、亡くなられた方ご本人に対する意識というのは、正直あまり強くはなかったんです。
ですが、初めて対面したときに、「この方の人生にはどんな背景があったんだろう」と強く思わされました。
自分にとっては受け入れがたい最期のかたちでしたが、もしかするとその方にとっては、それしか選択肢がなかったのかもしれない。
そう考えると、人の生と死、そして人生そのものの重みを一気に感じましたね。あれが私にとっての葬儀の原点だったと思います。
── 長谷川:本当に…人それぞれに人生があるということを強く実感されたんですね。 日々の生活では見過ごしがちなことかもしれませんが、そうした現場に立つことで「生きること」「死ぬこと」について真正面から向き合わざるを得なくなる──そんな感覚が伝わってきました。
高柳社長:そうですね。まさにそこから、葬儀の仕事は「単なる儀式」ではなく、人生の物語に触れる仕事だという意識に変わっていきました。
── 長谷川: そこから「やなぎ葬祭」として歩み始めてから「株式会社やなぎ」設立までの10年間、 やはりその間、不安やご苦労もたくさんあったのではないかと想像します。
高柳社長:そうですね。大きかったのは「葬祭業」という仕事自体が、今ほど社会的に認められていなかったということですね。
当時は、亡くなった方に関わる仕事ということで、あまり表立って「立派な職業だ」とは言ってもらえない雰囲気があったんです。
家族や友人も、正直ほとんどが反対でした。
それに、葬祭業は他の商売と違って、「今日オープンしました!セールやってます!」みたいな集客の仕方はできないんですよね。
なので、営業活動を地道に続けて、地域での信頼を一歩ずつ積み重ねていきました。
── 長谷川:試行錯誤の連続だったんですね。 そんな中で、お伺いしたいのですが、高柳さんご自身にとって、心の支えや原動力となったものはありましたか?
高柳社長:やっぱりいろんなことがありましたけれども、やはり一番は「人」でしたね。
最初は本当に売上もない状態でしたし、葬祭業って関わる範囲がとても広いんです。
霊柩車の手配もあれば、式の準備、会葬者へのお礼の品、そして何より、ご遺族の気持ちに寄り添うこと──。 どれも一人ではできません。
そんな中で支えになったのが、スタッフはもちろん、創業当初に手伝ってくれたパートの方や、外部の業者さんの存在です。
それに、専務──今の妻ですね──も一緒に踏ん張ってくれましたし、その家族、特にお父さんにも色々と協力していただきました。
こういう人たちがいたから、ここまで続けてこられたんだと思います。
自分ひとりじゃ絶対に無理だったと、今でもそう思っています。

インタビュー中、高柳社長が終始「自分は周りに支えられてきた」とお話しされていたのが、とても印象的でした。
── 長谷川:葬祭というお仕事は、人の死と向き合う──非常に繊細で責任のある仕事だと感じています。 決して「なんとなく」でできるものではないですし、だからこそ、携わる側の“心の構え”がとても大切だと思うんです。 高柳さんがこの仕事に向き合う上で、大切にされていることはどんなことでしょうか?
高柳社長:そうですね、よくある誤解なんですが、葬儀って「感情を抑える仕事」って思われがちなんですよ。
スタッフの中にも「泣いたらダメですよね」とか「笑ってはいけないですよね」って構えてしまう人も多いです。
── 長谷川:たしかに、そういったイメージはあるかもしれません。
高柳社長:でも、うちは違う考え方をしています。
“人が人として人と接する”というのが、一番大切だと思ってるんです。
悲しい時は泣いていい。笑う時は笑っていい。怒りが湧いたら、それも人として自然な感情。
それを封じてしまうと、ご遺族との距離も縮まらないんですよね。
遺族の方に「この人、なんでこんなに平気なんやろ?」って思わせたらダメなんです。
逆に、こちらも心から向き合って泣いたり、想いを馳せたりすることで、「この人に任せて良かった」と思っていただけるんじゃないかと。
── 長谷川:まさに、“家族の一員”のような距離感ですね。
高柳社長:そうなんです。もちろんスタッフには「感情を出すこと」を伝えていますが、最初はみんな戸惑いますよ。
泣くことに抵抗がある子も多いですし、どこまで踏み込んでいいのか悩むこともある。でも、勇気を出して一歩踏み込めば、ご遺族との間に信頼関係が生まれる。
そういう関係性が築けるかどうかが、この仕事の本質だと思っています。
── 長谷川:一つのお葬式を“ただの業務”としてではなく、「誰かの人生の締めくくり」として向き合う。 その覚悟と想いが、まさにやなぎさんの姿勢なんですね。ありがとうございます。

高柳社長のご息女・高柳有様とお客様のご様子。「感謝で送るお葬式」を形にし、人と社会を幸せにする会社を目指しています。
── 長谷川:ではここからは、実際にやなぎ様でご活躍されている社員の方にもお話を伺いたいと思います。 まずは吉井さん、やなぎに入社されたきっかけについて教えていただけますか?
吉井様:はい。最初は、学校に企業説明会として「やなぎ葬祭」さんが来られた時にお話を聞いて、直感的に「あ、ここで働きたい」と思ったのがきっかけです。
── 長谷川:その「やってみたい」という直感の中で、不安や迷いはありませんでしたか?
吉井様:やっぱり職種的に、親から何か言われるんじゃないかなという不安はありました。
でも実際は、「すごくいい仕事じゃん」って背中を押してくれて。 周りからも応援されて、面接の頃にはもう全然不安はなかったですね。
── 長谷川:ありがとうございます。では、現在のお仕事についても少し教えていただけますか?普段はどんな役割を担っていらっしゃるのでしょうか。
吉井様:はい。主に、お通夜やご葬儀の現場で、進行全体の監督やリーダー的な立場で動いています。
ディレクションのような役割ですね。
── 長谷川:現場の中心で、式全体をまとめていらっしゃるんですね。ありがとうございます。では吉井さん、実際にやなぎに入社されてから初めてお葬式の現場に立ったとき、どんなことを感じられましたか?
吉井様:最初は本当に複雑な気持ちでしたね。
やっぱり「泣いちゃいけない」「感情を出してはいけない」っていう意識が強くて、すごく頭の中が混乱していたのを覚えています。
── 長谷川:感情を出してはいけない、というのはやはり「葬儀の現場=淡々とこなすべき」というイメージがあったからでしょうか?
吉井様:そうですね。
社会人としても初めての会社だったので、どうふるまうべきかも全然わからなくて…。
「プロは冷静に対応すべき」と思い込んでいたんです。
でも現場に立つと、悲しみに寄り添う気持ちや、笑顔で思い出話に花を咲かせるご遺族の様子に触れて、「これは本当に感情を押し殺す仕事なのか?」と悩みました。
── 長谷川:今では、その感情との向き合い方はどのように変わってきましたか?
吉井様:一緒に泣くのはまだちょっと難しいですが、思い出話を聞いて笑顔で返す、共感するということは大切にしています。それもひとつのご遺族の心のケアだと思っていますし、今は“いい塩梅”で感情も出しながら接しています。
── 長谷川:素晴らしいですね。では、そんな中でこのお仕事に“やりがい”や“誇り”を感じるのはどんな瞬間でしょうか?
吉井様:ご葬儀って、結婚式と違って数日で終わるものなんです。その短い時間の中で信頼関係を築いて、「吉井さんでよかった」「ありがとう」って言っていただけることがあって。
大人になると、そんな心のこもった“ありがとう”を直接言われる機会ってなかなかないじゃないですか。
だからこそ、あの一言にすごく救われるんです。
── 長谷川:確かに、そんな言葉をもらえる仕事って貴重ですね。

普段の業務を行う吉井様の様子
── 長谷川:逆にこれまでで、特に大変だったことや、辛かった出来事があれば教えていただけますか?
吉井様:少し重たい話になりますが…以前、自ら命を絶った若い方のご葬儀を担当させていただいたことがあったんです。
その約1ヶ月後に、息子さんの49日を迎える前に、お父様も「息子のところへ行く」とおっしゃって亡くなられて…。
そのお父様のご葬儀も私が担当させていただいて。
そのときは本当にどう接すればよいかわからず、私自身も涙をこらえながら必死で対応しました。
元気とは言えなくても、前向きに頑張っている姿を見ていたので、あのときは本当に精神的にしんどかったです。
── 長谷川:聞いているだけでも胸が締めつけられるような経験だと思います…。それでも、しっかり向き合ってこられた姿勢に、心から敬意を表します。それでも、今もこうして現場に立たれているということは、その出来事を乗り越える何かきっかけがあったのではないかと思うのですが、どのように気持ちを整理して、今の自分に至っているのかをお伺いしてもよろしいでしょうか?
吉井様:そうですね…。そのご遺族の方、特に奥様がですね、息子さんも旦那さんも相次いで亡くされたという非常につらい状況の中でも、前を向こうとされていたんです。
もちろん、見ないようにしている部分もあったと思うんですけど、自分を奮い立たせて頑張っている姿を見て、「ああ、私が下を向いている場合じゃないな」と思ったんです。
── 長谷川:その姿に、心を動かされたんですね。
吉井様:はい。今でも時々様子を伺いに顔を見に行ったりしています。
ご遺族の心のケアの一環として、自分にできる範囲で寄り添うようにしていて、その方が頑張っているからこそ、私も支える側として、背中を向けちゃいけないなって思えるようになったんです。

葬祭ディレクターは、ご家族様の声に耳を傾け、亡くなられた方がどう生きてこられたのかを皆さんで想い出に振り返る時間と空間創りをするお仕事です。
── 長谷川:お葬式が“終わり”ではなく、“新しい始まり”を支える仕事でもあるのだなと、あらためて感じさせていただきました。 では次に、このお仕事を通じて「自分が成長できた」と感じることがあれば教えていただけますか?
吉井様:ほんの些細なことなんですけど…。
私はもともと話すのは得意だったんです。でも、聞くのは正直そんなに得意じゃなかったんですよね。自分のことを話すのは好きでも、人の話をじっくり聴くのはあまりできなくて。
でもこの仕事を通じて、お客様との対話の中で“聞く力”の大切さをすごく実感して、少しずつですが、自分でも「聞き上手になれたかな」って思えるようになりました。
それは仕事だけじゃなく、プライベートでもすごく活かされています。
── 長谷川:素晴らしい変化ですね。では最後に、「この会社、この仕事に向いている人ってどんな人だと思いますか?」という問いにもお答えいただけますか? ざっくりでも構いません。
吉井様:そうですね…やっぱり、話すのが好きな人、聞くのが好きな人には向いてると思います。
「感情に寄り添える人」とも言えるかもしれません。あと、意外かもしれないですけど、明るい雰囲気の人も向いてると思うんです。
── 長谷川:なるほど。お葬式の現場って“静かで厳かな場”という印象があるので、明るい方が向いているってちょっと意外でした。
吉井様:たしかにそう思われるかもしれないんですけど、実はその明るさに救われるご遺族もたくさんいるんです。
全員が全員に合うわけではないですけど、「この人が担当でよかった」と言ってもらえるのって、少しでもそうした雰囲気を感じてもらえたからだと思うので。
── 長谷川:本当に貴重なお話をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました。これからやなぎで働いてみたいという方にとって、すごくリアルで、心に残るインタビューになったと思います。
吉井様:こちらこそ、ありがとうございました。
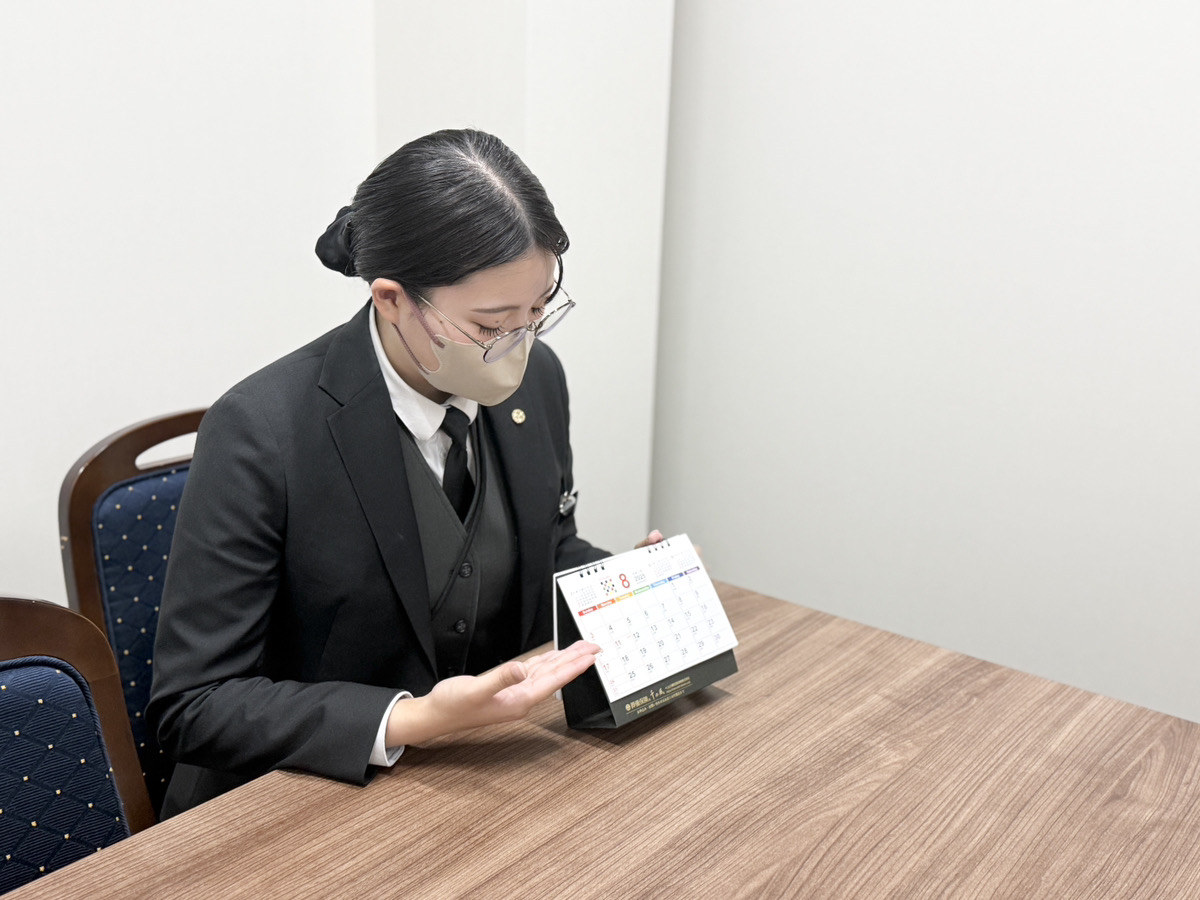
「この人が担当で良かった」そう感じていただけるよう、一つひとつのご提案や対応に心を込めています。
── 長谷川:それでは最後に、改めて社長の高柳様にお伺いさせていただきます。 今後、どのような会社を目指していきたいとお考えでしょうか?
高柳社長:今は「葬祭業」という形で事業を行っていますが、最近では「供養業」と言ったほうがしっくりくるかもしれません。というのも、昔に比べて供養という文化や価値観が、少しずつ薄れてきているように感じていまして。
── 長谷川:たしかに…現代ならではの感覚の変化はありそうですね。
高柳社長:ええ。最近は「お墓はいらない」「仏壇も置かない」「お骨も手元に残さない」といった方も増えてきています。
もちろん全員ではありませんが、やはりそうした価値観の広がりを肌で感じるようになりました。
でも本来、供養って、亡くなった方のためだけではなく、残された人の心を整えるためのものでもあると思うんです。
── 長谷川:まさに残された方にとっての“区切り”や“始まり”でもありますよね。
高柳社長:そうです。供養ができない人は、自分自身も供養されなくなる──そんな考え方もあるくらいで。
昔はお寺さんや地域のコミュニティ、家族や親戚が自然とその意味や所作を教えてくれていたんですが、今はそうしたつながりがだんだん薄れてきている。
だからこそ、私たち葬儀社が、その役割を担っていくべきだと感じています。
── 長谷川:葬儀という形式だけでなく、文化や人の心に向き合う存在としての使命ですね。
高柳社長:おっしゃる通りです。やなぎとしては、無理にエリアを広げるつもりはありません。
この地域に根差して、「やなぎがあってよかった」と言っていただけるような存在になりたい。
私たちが担う“供養”を通じて、この地域をもっと優しく、温かくしていく──それが、私たちの目指す会社の姿です。

2024年7月、三重県の葬祭業で初となる「ホワイト企業認定」を取得。
── 長谷川:ここまでお話を伺っていても、御社が“人”を本当に大切にされていることが伝わってきました。その中で、スキルや経験以上に「こういう人と一緒に働きたい」と思えるような人間性があれば、教えていただけますか?また逆に、「こういう価値観の人とは少し合わないかもしれない」と思うものがあれば、そちらもお聞かせいただけると嬉しいです。
高柳社長:そうですね…。この“価値観”って言葉は、すごく難しいなと感じることもあるんですが、僕は、人の価値観って「変わるもの」だと思ってるんです。
やっていく中で、環境が変われば考え方も変わる。だから最初から価値観が合わないからダメ、という判断はしません。
── 長谷川:なるほど。育ってきた環境も違えば、考え方が違うのも当然ですもんね。
高柳社長:はい。ただ、お葬式に関わる仕事って、人の最期に立ち会う仕事ですから、自然と自分の考え方も変わってくるものなんです。
だからこそ、「価値観が違う=一緒に働けない」とは思わない。
一緒に働いていく中で、気づけばお互いの考え方が近づいていく。逆に、合わなかったら、自然と離れていくだけかなと。
── 長谷川:すごく柔軟なスタンスですね。では、あえて挙げるとすれば「こういう人は合わないかも…」というポイントはありますか?
高柳社長:あえて言うなら…「嘘をつく人」と「人の悪口を話題にする人」ですね。
例えばその場にいない誰かのことを、陰で話題にするような人。
合う合わないって、結局“信頼”があるかどうかだと思っていて。嘘や悪口があると、やっぱり信頼関係が築けないんですよね。
── 長谷川:たしかに、チームの空気や働く環境にも直結してきますよね。
高柳社長:そうなんです。スキルや経歴よりも、そういう“人としての誠実さ”の方が、よっぽど大事やと思っています。

ご家族様より素晴らしい評価のアンケートをいただいたスタッフへ、毎月の全体会議にて表彰式を行っています。
── 長谷川:「信頼できる人と、正直に向き合えるチームをつくる」──それが、御社の考える“理想の職場”なんですね。ありがとうございます。では最後に、これからやなぎで一緒に働く仲間に対して、どのようなことを大切にしてほしいとお考えでしょうか?
高柳社長:そうですね、やはり「一緒に働く仲間」としての意識を大切にしてほしいです。
吉井も話してくれましたが、仕事を通じて自分が得た経験や学びというのは、次に入ってくる誰かにぜひ繋げていってほしい。
人を育てるというのは、自分の成長にもつながります。教えてもらう側から、教える側へ。
そういうバトンをつなぐ職場であってほしいし、その連鎖こそがやなぎの文化だと考えています。
── 長谷川:本当に、“次に繋げる姿勢”が組織全体に根付いているんですね。
高柳社長:この葬祭の仕事って、一見すると重くて構えてしまう方も多いかもしれません。
でも実際には、すごく“プラスになる仕事”なんです。
まずは、やりがい。
残されたご家族が、これからどう歩んでいくか――その人生の節目に立ち会って、一歩踏み出す支えになれる。
ご家族から「あなたで良かった」と言っていただけたときの喜びは、他の仕事にはなかなかないものだと思います。
そしてもう一つは、人としての成長です。
お客様との対話や、ご縁の中で、多くの人生に触れ、自分のこれまでの生き方や、これからの人生についても自然と考えるようになる。
家族や友人のこと、自分の時間の使い方――そういうものに改めて向き合えるのが、この仕事のすごく価値ある部分だと思っています。
── 長谷川:ありがとうございます。お話を伺いながら、私自身も「悔いのない人生を生きたい」と自然と思わされるような、不思議な感覚になりました。ここまでインタビューさせていただく中で、御社のお仕事の見え方が大きく変わった気がします。
本当にお時間をいただき、ありがとうございました。
取材者のレビュー
取材を通じて特に心に残ったのは「すべては人とのご縁から始まる」という高柳社長の言葉で、その考えが事業の根底を支えている点です。
葬儀を「人生の終わり」ではなく「残された家族の新しいスタート」と捉える視点に触れ、供養の意味を改めて考えさせられました。
また、現場で働く吉井さんの姿からは、感情に寄り添いながら前を向くご遺族を支える強さと優しさが伝わってきました。
高柳社長の言葉と社員の実践、その両方が重なり合うことで「やなぎ」という会社の温かさが形づくられているのだと感じました。

長谷川 颯汰
前職では、不動産投資の営業として、お客様の資産形成やライフプランに関わる提案業務を経験。2024年より株式会社ソビアに入社し、ホワイト企業認定の運営に従事。認定企業様の魅力を丁寧に言語化し、ホワイトキャリアを通じて多くの方へ届ける仕事に取り組んでいます。