

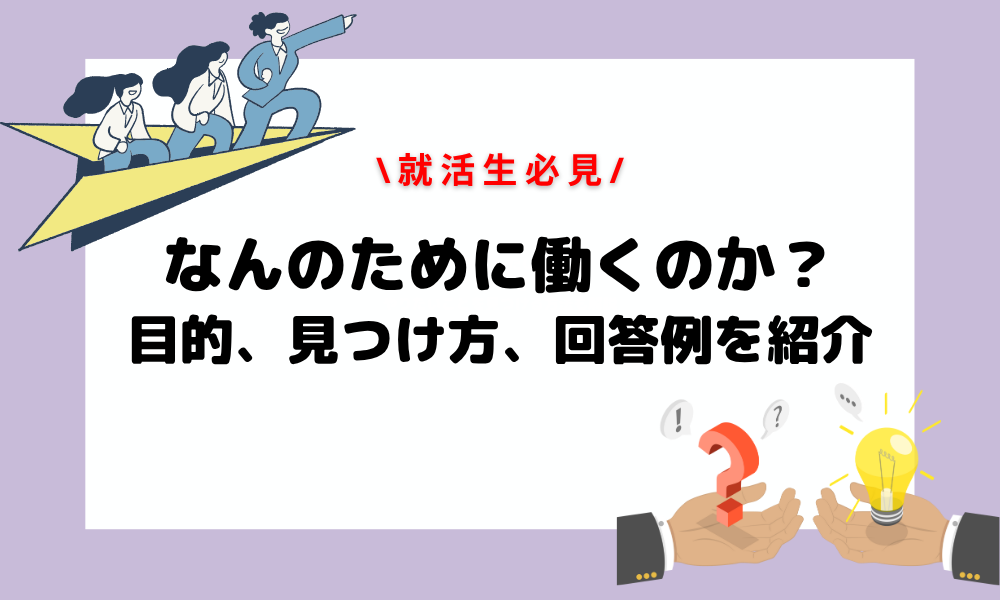
大学卒業後、院への進学や海外留学を除くと、多くの方はなんらかの仕事に就きます。しかしなかには「周りに合わせて就活しているけれど、なんのために働くのかわからない」「面接で働く意味を聞かれて、うまく答えられなかった」と感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、なんのために働くのか、一般的な目的や、自分にとっての理由の見つけ方について解説します。

なんのために働くのかと問われたとき、出てくる答えは人によってさまざまです。ここでは、よくある8つの働く意味を解説します。
8つの中で、いずれかに共感できるものがあれば、それはあなたの働く意味に近いといえるでしょう。
生活費を得る手段として仕事があります。実家や親戚に農業や漁業に関わっている方がいる場合、お金を払わなくても食料は手に入るでしょう。しかし、衣服や家具、ガソリンといった現物や水道光熱費などは、お金がなくては購入したりサービスを利用したりできません。
仕事をして生活費にあてられる収入が得られれば、安心につながります。
仕事は、自分の能力を活かせる場でもあります。努力して身に付けた知識やスキルを発揮できる職場で、仕事を成功に導くことができると、達成感を味わいつつ実績も積んでいけます。
なかには、趣味で特定の分野に詳しかったり、資格を取得したりした方もいるのではないでしょうか。仕事内容に関係する分野なら、専門性が高い人材として周囲から頼りにしてもらえます。また、業種が異なる職場でも、趣味で身に付けた能力が役立つこともあります。
サービス業など、多くの人の役に立っていると実感しやすい仕事は、社会貢献への意欲が高い方に適しています。
自分が毎日取り組んでいる仕事で誰かの役に立っていることを実感すると、モチベーション向上や働く意味にもつながります。
やりがい・達成感は、仕事の生産性にも影響する大切な要素です。人によっては、やりがい・達成感を実感できることに魅力を感じて特定の仕事に従事している場合もあります。
内閣府の働く目的に関する調査では、「生きがいを見つけるために働く」と答えた方の割合が12.8%でした。「自分の才能や能力を発揮するために働く(7.2%)」よりも割合は高く、仕事でやりがいを重視する方は少なくないといえます。
やりがい・達成感は、自己成長にもつながります。
出典:内閣府「国民生活に関する世論調査(令和5年11月調査)」
職業は社会的な信用にも大きく関係します。例えば住宅を購入するとき、ローン審査で重視されるのは、安定した収入を得られることや勤務先の社会的信用度が高いことです。必然的に、自営業やアルバイトよりも正社員のほうが審査に通りやすくなります。
勤務先企業や雇用形態に加えて、勤続年数も信用度を左右する要素のひとつです。同じ企業に長年勤めている人材なら、根気があり業界に詳しいと評価されます。
仕事内容のみならず、働くこと自体を通じて、社会的な信用を築いていけます。
仕事を通じて社内外の多くの方と関わる機会があります。このような社会とのつながりが、今後のキャリア形成に大きな影響を与え、ひいては人生においても重要な意味を持つことになります。
例えば仕事の中で誰かと支え合ったり、自分とは考え方が異なる相手と上手に付き合ったりした経験は、プライベートでも役に立つでしょう。成功体験や人とのつながりが、仕事へのモチベーション向上にもつながります。
仕事でお金を稼ぐと、プライベートの充実も叶います。欲しいもの、行きたい場所、体験したいことの多くは、実現するためにはある程度の金銭が必要です。
目標額を貯める過程で挫折しそうなことがあっても、「〇〇に絶対に行きたいから」「□□を買うため」と実現したいことがあれば、モチベーション低下を防いでくれます。
近年、若い世代を中心に、推し活のために仕事を頑張るという意識が浸透しつつあります。プライベートを自分らしく生きるためにお金を稼ぐことも、立派な働く理由のひとつです。
現状の生活費に加えて、将来のための備えとしてお金を稼ぐ必要があります。人生は結婚、出産のような、ある程度は予測できる出費ばかりではありません。突然の病気や事故、介護などは、準備する余裕もなく出費が発生します。
上記のような「もしものとき」に備えて貯金するために、お金を稼ごうと考える方もいます。

就職活動を進める中で、「なんのために働くのだろう」「本当にこの道で良いのかな」と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
まずは自分がなんのために働くのかわからなくなった原因や、仕事について考えてみましょう。
自分のやりたいことが見つかっていない場合、言語化しにくい焦燥感が胸にくすぶっていることがあります。生活のためにとりあえず働いている方は、将来への不安や周囲との差に不安を覚えて、「なんのために働いているのか」がわからなくなってしまうことがあります。
まずは自己分析で自分が本当にやりたいこと、興味のあることを洗い出し、「仕事をするための目標」を見つけることが大切です。
自分の性格や能力が何に向いているのかわからないことも、職業選びで悩む理由のひとつです。適職を考える上で理解しておきたいのが、やりたいこと・興味のあるものが必ずしも自分に向いているとは限らないことです。
自分の実力を十分に発揮できる業務や、結果や過程に満足できる仕事なら、好き嫌いの感情に関係なく適職といえます。
自分に合う職業がわからない方は、適職診断をしてみるのも良いでしょう。複数の診断サービスを利用すると、自分に合った仕事や業界を見つけやすくなります。
働くこと自体にネガティブなイメージを持っている場合、就職活動や将来への意欲を維持しにくくなります。
例えば、以下のような不安を抱えていないでしょうか。
・親や周囲から「働くのは大変」と聞かされている
・アルバイト経験で嫌な思いをした
・とにかく「働きたくない」という気持ちがある
・失敗して怒られるのではないかと不安に感じる
・ブラック企業のニュースを見て働くことが怖い
など
働くことに対して不安やストレスを多く抱えていると、「どうして働かなければいけないんだろう」と働くこと自体に抵抗感や違和感が生まれます。
ネガティブなイメージを払拭するためには、自分が働くことの何に不安を感じているのか自覚することが大切です。働くことへの不安の原因を、紙に書き出して整理してみましょう。不安の原因を参考にすると、自分に合った職種や働き方が見つかることがあります。
心身が疲れていると働く意味を見失いやすくなります。就職活動で忙しかったり、アルバイトと学業の両立で疲れていたりと、生活リズムが乱れて余裕がない状態になっている方は、注意が必要です。
なんのために働くのかわからなくなるうえ、人によっては身体を壊すおそれもあります。就職活動や勉強・アルバイトに追われて十分な休息が取れていないと感じたら、信頼できる相手や学生相談室などに相談することも大切です。

働く目的がわからなくなることは、誰にでも起こり得ることです。悩んでいるときは焦りや孤独を感じる場合もありますが、深刻に捉える必要はありません。
もし「なんのための働くのか」がわからなくなったときのために、あらかじめ対処法を知っておきましょう。対処法がわかっていれば、不安や悩みを解消するヒントとなります。
ここでは「なんのために働くのか」理由を見つける方法を解説します。
働く上でブレてはいけないポイントが、自分の価値観や強みです。将来のキャリアを考えるときも、自分の価値観や強みを活かせるプランを設計しましょう。
価値観が明確になれば、働く目的が見えてきます。強みも考慮すれば、将来のためにやるべき行動も洗い出せます。
価値観や強みを見つけたいときは、ライフチャートやSWOT分析がおすすめです。
・ライフチャート:横軸を年齢、縦軸を幸福度(充実感)として過去の経験を曲線で表す方法
・SWOT分析:自分を「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4フレームで整理する方法
ライフチャートは過去の経験や出来事について、幸福や充実を感じた瞬間を視覚的に整理できます。SWOT分析は仕事やキャリアの状況を4つのフレームに分けて整理することで、今後取るべき行動がわかります。
ライフチャートを利用した自己分析を参考に、過去の経験を詳しく振り返ってみましょう。どのようなときに喜びや充実感を得たのか、反対にどのような場面で挫折感やストレスを感じたのか整理します。
喜びや充実感を得た瞬間が働くことと関係のある場面なら、働く理由につながります。
例えば「アルバイト先でお客様から直接お礼を言われたとき、嬉しかった」「部活動で後輩に教えて成長を見守れたとき、充実感があった」という経験からは、人の役に立つことが好きなのだと気付きを得られるでしょう。
理想の自分を思い描いて行動すると、達成感ややりがいを得られます。スムーズに思い浮かばないときは、働き方や生き方が素敵だと感じる社会人の先輩や、憧れの職業の人を参考にするのもおすすめです。
その人のどのような点が尊敬できるのか、自分も同じようになりたいと思う部分はどこなのか整理します。アルバイトや学校生活で実践できそうなところから真似をして、自分自身の言動を理想の働き方に近づけていきましょう。
理想の働き方に近付くと、仕事との向き合い方が変わり、疑問や違和感から解放されます。
就職活動や将来に向けた小さな目標を立てると、モチベーション維持につながります。
長期的なキャリア目標のような大掛かりなものではなく、例えば「今日は企業研究を1社分進める」「明日までにエントリーシートを1つ完成させる」といった日々の取り組みをリスト化して、ひとつずつ達成するごとにチェックしていく程度で十分です。
アルバイトや学業での日々の取り組みもリスト化してチェックしていくと、1日のうちに何度も小さな達成感を得られます。小さな成功体験を積み重ねれば、働くことの楽しさや意味に気づけます。

働く目的は、個々人によってさまざまです。お金のために働く方もいれば、社会的な価値のために働く方もいるでしょう。大切なのは、自分がなんのために働くのかを言語化することです。
ただし、この言語化が非常に難しくもあります。ひとつの方法として、過去の自分の経験を振り返り、熱量高く取り組めた時はどのような出来事だったのかを見つけましょう。その出来事の中に、自分が大切にしている価値観が見つかるはずです。その価値観をベースに働く目的を考えていくと、上手く言語化できるようになるでしょう。

新卒の就活や転職時の面接で、採用担当者から「なんのために働くのか」「働く目的はなにか」と質問されることがあります。
採用担当者が面接の場で働く目的を聞く理由は、以下の通りです。
・仕事観が自社の社風に合っているか確認するため
・どのような目的意識で仕事に臨んでいるか知るため
・仕事に対する意欲をはかるため
・長く働く意思があるか知るため
前述の通り、働く目的は生活のためだったり、プライベートを充実させるためだったりする方もいます。しかし面接の場でそのまま答えると、「自分のことしか考えていない」「質問の意図を理解していない」とマイナスの評価につながりかねません。
面接の場で働く目的について聞かれたときは、選考の一環として質問されていることを理解して、自己アピールとなる回答を選びましょう。
以下で回答例を紹介します。
【回答例1】
「私は、仕事を自己成長の機会と考えております。毎日帰宅する電車の中で1日の業務についてひとり反省会を行っており、次はどのように対応すべきか解決策を出してから就寝するようにしております。
御社は部下が上司を評価する制度を取り入れており、風通しの良い社風が魅力的であると感じました。上司と部下が互いに評価し合い、高め合える環境で成長して、御社の発展に貢献していきたいと考えております」
【回答例2】
「私にとって働く理由は、社会貢献をしつつ自分自身も成長することと考えております。御社が運営されている〇〇ホテルは、何度も利用させていただいています。建物内で忙しそうにすれ違うスタッフの皆さんは、常に笑顔できびきびと働いており、その洗練された姿勢から仕事への愛情が伝わってきます。
私も入社後は、お客様が気持ち良く過ごせるように笑顔を絶やさず、いつ来ても気持ちの良いホテルだと評価していただけるよう、尽力していきたいと考えております」
【回答例3】
「私にとって、仕事をする意味は自分の愛する故郷を守ることだと考えております。私の地元は漁港として発展しており、環境問題の影響を日々の生活の中で実感してきました。御社が取り組む環境保護活動や革新的な製品は、土壌のみならず海の保全にもつながると感じております。
私が入社したら、環境保護につながる製品を幅広い業種のお客様の元へ届けていき、ゆくゆくは故郷の海を守ることにつなげたいと考えております。」
働く目的は人によってさまざまです。なんのために働くのか理由が見つからないときは、自分は仕事で何を得たいのか、他の方の回答に共感できるところはあるのか考えてみることが大切です。
働く理由が見つかれば、就活やキャリア形成で譲れないものや守りたい価値観に気づけます。面接で聞かれることもあるので、自分なりの答えを見つけておきましょう。