

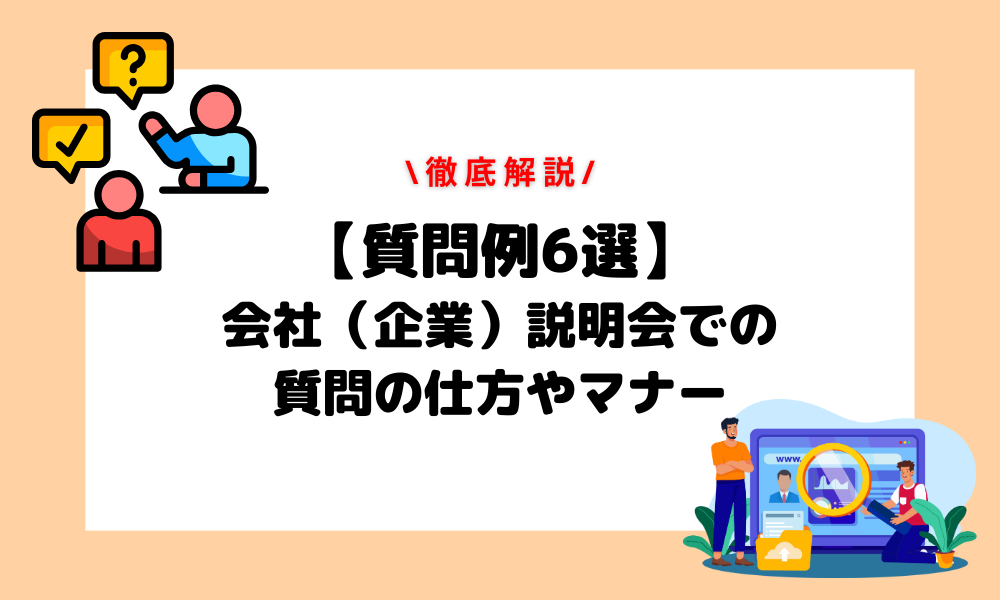
就職活動をスムーズに進めるためには、会社説明会へ積極的に参加することが大切です。会社説明会は、興味をそそられる企業を探すための単なるイベントではありません。
会社説明会をいかに有意義に過ごせるかが、今後の就職活動に大きく影響します。
今回は、対面開催での会社説明会へ初めて参加する方や、より有意義な時間にしたい方へ向けて、効果的な質問やマナーを解説します。
目次

多くの企業では、会社説明会が終盤に差し掛かるタイミングで、就活生からの質問を受け付ける時間を設けています。時間の都合上、必ず質問できるとは限らないものの、積極的に参加することをおすすめします。
会社説明会の質問タイムは、今後の就活にも大きく影響する重要なポイントです。真剣に取り組むべき理由として、次の2つがあげられます。
コーポレートサイトや求人サイトの閲覧のみでは、限られた情報しか入手できません。会社説明会で業界や企業について気になることを質問すると、インターネットでは得られない情報も獲得でき、理解を深められます。
業界・企業の理解度が高くなると、他社との比較も容易です。企業側も自社で働く自分の姿を具体的にイメージしてもらうために、会社説明会でさまざまな情報を提供しています。
会社説明会で企業の理解度を高めるためには、従業員の1日のスケジュールや業務内容、業務外のイベントなど、気になることは細かく質問することが大切です。疑問点を放置していると、面接時や入社後のミスマッチにつながります。
質問ややり取りを繰り返す中で、社風や従業員の人柄もわかるようになります。
会社説明会の段階で、採用担当者の印象に残る可能性があります。会社説明会は、学生が業界・企業について学べると同時に、採用担当者に自分の顔や名前を覚えてもらえる場です。
質問の内容ややり取り、イベントに臨む姿勢で、採用担当者に強く印象づけましょう。会社説明会の規模や方法によっては、行儀良く参加しているのみでは、採用担当者に見てもらえないおそれがあります。
少しでも印象を残す効果的な方法が、会社説明会の後半に設けられる質問タイムです。質問は積極性のみならず、事前に企業についてしっかり調べていることもアピールできるチャンスです。採用担当者に好印象を残せることもあるので、遠慮せず積極的に質問することをおすすめします。

会社説明会で質問するからには、採用担当者の印象に残ることを言いたいものです。しかし、目立とうとして的外れな質問をすると、かえって悪目立ちしかねません。
大前提として、就職活動に活かせる質問をすることが求められます。ここでは、会社説明会で聞いておきたい基本的な質問例を6つ解説します。
会社概要・事業内容に絡めた質問は、企業にどれだけ興味があるのかを伝えられます。どこまで理解しているのかを質問に織り交ぜれば、入念に調べた上で疑問に思ったことを質問しているとアピールできます。
質問内容を考えるときは、単純な質問で終わらないように注意しましょう。内容が薄いと、よく調べずに参加していると誤解されかねません。
特に会社概要・事業内容の基本情報はコーポレートサイトなどさまざまな場ですでに公開されているため、質問時は深掘りした内容が求められます。
「競合他社が〇〇方向に戦略を打ち出している中、御社が△△の方針を選んだ理由を教えてください」
「御社の商品に共通する強みは〇〇とのことですが、他にも企画時に重視している点を教えてください」
「御社の〇〇事業に興味をもっております。新入社員や若手が〇〇の事業に携わった実績はありますか?」
「御社は昨年、海外進出をされましたが、〇〇の地域を中心に展開している理由について教えてください」
など
強みやビジョンは、コーポレートサイトや求人サイトに記載されていることもあります。また、同じ会社説明会の会場で他の就活生が先に質問する可能性もあるため、重複しないように注意が必要です。
規模が大きな企業は、強みや方針が分かりにくい場合もあります。企業研究のみでは分からなかった部分を集中的に聞きましょう。

会社説明会には、採用担当者や代表の他に先輩従業員が参加していることもあります。実際に働いている人の目線で、仕事内容について知るチャンスです。
今後の就職活動に活かすためには、現状に加えて新入社員のころの仕事内容についても聞いておきましょう。先輩の新入社員時代を知ることで、入社直後のミスマッチ予防にもつながります。
質問するときは、できる限り具体的な回答をもらえるような言い回しを意識することが情報を引き出すコツです。
「1日のスケジュールについて、仕事の流れを大まかに教えてください」
「新入社員のときに、力を入れて取り組んでおいて良かったことは何ですか?」
「〇〇の事業に興味があります。仕事をする上で役立っている資格を教えてください」
「これまでの業務の中で、もっとも困難だったことは何でしょうか。乗り越えた方法も教えていただきたいです」
など
仕事内容に関する質問は、従業員や社内の雰囲気を知ることにもつながります。自分が働くシーンを具体的にイメージできるように、踏み込んだ内容を意識することが大切です。
社風は、インターネットに掲載されている情報のみでは分かりません。一方で、モチベーションを維持しつつ働くためには、軽視できない要素です。
会社説明会では実際に働いている従業員の雰囲気を確認しつつ、社風に関する質問で自分との相性を判断しましょう。従業員が職場でどのようなことを感じているのか聞くと、自分が理想とする職場とのマッチ度が分かります。
「御社の社風について、入社後にギャップを感じた部分はありますか?」
「御社の魅力は、若手が意見を言いやすいことだとうかがいました。若手の意見が反映された事例について教えてください」
「従業員の方は、どのようなタイプの方が多いのでしょうか。年齢や男女比とともに教えていただきたいです」
「他部署との交流はありますか?」
など
複数の従業員が会社説明会に参加している場合、社風を一言で表すと、それぞれどのような言葉になるか聞くのもおすすめです。複数人が簡潔に答えられる質問なら、さまざまな視点で社風について教えてもらえます。
上司や先輩との関係性や困ったときの相談の仕方について質問して、人間関係から社風を知る方法もあります。

働き方に関する質問も、言い回しや内容に注意すれば問題ありません。注意点は、条件のみを聞きすぎないことです。条件に関する質問が多いと、企業ではなくメリットで志望先を選んでいると誤解されるおそれがあります。
あくまでも企業や仕事について知るための質問であることが伝わるように、言い回しや内容のチョイスに配慮しましょう。聞きたい部分が同じでも、質問の仕方によって相手に与える印象は大きく変わります。
「内定者インターンシップの制度はありますか?」
「御社は男性従業員の育児休暇取得に積極的だとうかがいました。実際の取得率を教えてください」
「御社は独自の福利厚生が多くありますが、○○さんが中でも特に嬉しいと感じている福利厚生は何でしょうか」
「御社の繁忙期・閑散期について教えてください」
など
近年は育児休暇や介護休暇の取得推進に積極的な企業が増えているものの、実際の取得率が高いとは限りません。ストレートに「育児休暇は取れますか?」と聞くと、条件重視の就職活動をしているように受け取られるおそれがあります。
同じ質問でも、「育児休暇の取得率を教えてください」と実績について聞くほうが好印象です。残業時間についても、直接質問するよりも繁忙期や閑散期に関する質問をして、ワンクッション設けたほうが担当者は気持ち良く話してくれます。
キャリアパスとは、組織内でステップアップするために必要となる過程のことです。将来的に希望の仕事や役職に就くためには、事前に社内の評価システムやキャリアパスを確認しておく必要があります。
求人サイトにキャリアパスの例が掲載されている場合はあるものの、あくまで標準的な情報です。従業員が実際にどのようなキャリアパスを歩んでいるのか、会社説明会で深掘りしておくと、入社後のミスマッチを避けられます。
自分は入社後どのようなキャリアパスを描くべきなのか、希望の役職につくチャンスはあるのか、質問で探りましょう。
「御社の〇〇職種に興味があります。どのようなキャリアパスがあるのか教えてください」
「将来的には〇〇のポジションを目指しております。キャリアパスの事例を教えてください」
「御社のキャリアアップ支援は、どのようなものがありますか?」
「御社には定年後の再雇用制度がありますが、実際に制度を利用されている方の割合を教えてください」
など
近年は定着率や生産性向上の観点から、多くの企業が従業員のキャリアアップ支援に積極的です。具体的にどのような支援があるのか、詳しく聞いておくとキャリアプランの設計に役立ちます。
なかには社外でのスクール受講や検定受験にかかる費用をサポートする企業もあるため、気になる方は利用者の事例とともに確認することをおすすめします。

選考に進んだときのことを考えて、企業がどのような人物像を求めているのか、どのような点に注目しているのか質問しましょう。
求める人物像が分からなければ、自分と合わない企業への応募で無駄な時間を費やすリスクがあります。仮に入社したとしても、社風と合わずに早期離職するかもしれません。
効果的にアピールするのみならず、入社後のミスマッチを防ぐためにも、企業が求める人物像は詳しく把握しておくことが大切です。
「若手社員には今後どのように成長してほしいと思っていますか?」
「御社が求める人物像にもっとも近い従業員の方は、どのような資格をお持ちでしょうか」
「御社で特に活躍している方々には、共通点はありますか?」
「○○さんが一緒に働きたい、この人になら仕事を任せたいと思う人物像を教えてください」
など
企業が求める人物像を知ると、入社後の目標にもなります。目指すべき人物像と近い部分があれば、面接時の自己PRにも活用しましょう。
性格や仕事への取り組み方に加えて、理想の人物像がもっている資格やスキルについての質問も効果的です。

会社説明会では、質問するときの態度も大切です。多くの学生が、担当者に少しでも自分のことを覚えてもらおうと積極的に質問します。担当者が感心するような質問内容を考えるのみならず、洗練されたマナーで質問タイムに臨むことも、良い印象を残すコツです。
質問をするときに心がけておきたいマナーは、次の6つがあげられます。
質問するときは、最初に大学名と名前を伝える必要があります。最初に名乗るのは、社会人としての基本的なマナーです。また、名乗ることで企業側の担当者も誰が発言しているのか把握しやすくなり、印象に残る可能性が高くなります。
会社説明会の場で基本的なマナーを守ると、相手に丁寧な印象を与えられます。名乗らずに質問を始めると、マナーがなっていない人・基本的な準備すらしていない人と、企業側にマイナスな印象を与えかねません。
会社説明会の質問タイム以外にも、就職活動中は何度も名乗る機会があります。普段から心がけて、大学名も忘れずに伝えられるように練習しておくことが大切です。
名乗るときの注意点は、大学名を省略せずに伝えることです。評価につながる可能性もあるため、立ち上がってハキハキと聞き取りやすい声で「○○大学△△学部の□□と申します」と告げてから質問に移りましょう。
学部名・学科名の正式名称が長く、質問時間を圧迫しそうな場合、大学名と個人名以外は省略しても構いません。
質問はできる限り簡潔にまとめて、間延びした内容にならないように注意しましょう。結論や重要な部分を最初に話して、具体的に何が聞きたいのかを明確にすると、相手に伝わりやすくなります。
長すぎる質問は、下記のデメリットにつながります。
・質問の意図が伝わらない
・担当者から欲しい回答が得られない
・担当者にマイナスの印象を与える
・他の質問に割く時間がなくなる
例えば緊張のあまり、質問をしたくなった経緯や理由から話す方もいるのではないでしょうか。
冗長的な話し方は、何を知りたいのか、どこが話の主題なのかが相手に伝わりません。質問の意図が伝わらなければ、担当者から欲しい回答を得られず、自分や周囲の就活生の時間までも無駄にするおそれがあります。
質問は事前にメモしておき、簡潔に伝えられるように準備しておくことが大切です。
「御社の〇〇についての質問です。御社の新事業として□□がありますが…」と、最初に何について聞きたいのかを告げてから、補足を加えましょう。

複数の質問をしたいときは、最初に伝えましょう。「2点質問があるのですが、よろしいでしょうか」と先に確認すると、担当者も時間配分しやすくなります。
事前に質問の数を伝える方法は、質問者側にもメリットがあります。
会社説明会に参加している就活生は、自己アピールしたい方や、企業研究を進めたいと考えている方がほとんどです。企業側も、できる限り多くの学生に質問の機会を与えたいと思っています。残り時間によっては、質問はひとり1つに限定されることがあります。
最初に複数の質問をしたいと伝えると、万が一「時間がないので1問まで」と断られても、優先順位を考えて発言できます。最初に何も伝えずに続けて複数の質問をしようとすると、途中で止められてもっとも知りたいことを聞けずに終わるかもしれません。
担当者からの印象を良くすることに加えて、優先順位の高い質問を確実に繰り出すためにも、最初に複数聞いても良いかどうかを確認しましょう。
また、複数質問したい場合も、時間をかけ過ぎないように2点程度に留めることが大切です。
質問に対する回答をもらった後は、必ずお礼を伝えましょう。回答の内容が想像とは異なっていたり、納得できなかったりしても、お礼を口にすることは最低限のマナーです。
シンプルに「有難うございます」と伝える程度で十分です。より担当者に好印象を与えたいときは、「ご丁寧に回答いただき、有難うございます」と伝えれば、他の学生に差を付けられます。
「御社のことを、さらに深く知ることができました」と、疑問が十分に解消できたことを伝える言い方も効果的です。きちんとお礼を言うことで、自分のために時間を割いてくれたことへの感謝を示せるのみならず、礼儀正しさもアピールできます。
冒頭の大学名や名前と、質問後のお礼は、緊張すると忘れやすくなります。最初に大学名・名前を言い、お礼で終えることをセットにして覚えておくなど、緊張しても忘れずにこなせるように練習しておくことが大切です。
企業の担当者は、回答を聞いているときの姿勢もチェックしています。背筋を伸ばして、全身で相手の話に集中しましょう。相手の目を見て話を聞くと、回答を真剣に受け止めていることが伝わります。
質問に回答してもらっている間、よそ見をすることはもちろん、スマートフォンを見ることも失礼にあたります。緊張し過ぎて無意識にスマートフォンを見ないように、注意が必要です。
ただし、回答内容に応じてメモを取るのは問題ありません。途中で気になる部分が出てきたからといって、相手の話を遮るのはマナー違反です。担当者から他に質問はないか確認されたとき、改めて踏み込んだ内容を質問するとスマートな印象をもってもらえます。
自分の質問が終わった後も、聞く姿勢は保つことが大切です。他の就活生が質問している間の姿勢も、担当者に見られています。油断してスマートフォンを見たり下を向いたりしないように注意しましょう。
他の就活生はどのような質問をしているのか、どのような回答があるのか真剣に聞くと、企業研究の参考にもなります。
回答してもらっている間は、適度にリアクションすることも好印象を得るコツです。無表情や無反応で回答を聞いていると、関心がない・真剣に取り組んでいないとマイナスに受け取られるおそれがあります。
適度な相槌を打ったり頷いたりして、回答に集中していることや話を理解しようと努力していることを伝えると、担当者からの高評価につながります。特にオンライン説明会の場合、カメラ越しでは表情の変化が伝わりにくいため、しっかりリアクションできているかどうかが大切です。
しかし、リアクションをとりすぎると不自然な印象を与えかねません。自然な反応を心がけましょう。

企業の深い事情まで探れる場とは言え、会社説明会ではマナーとして避けるべき質問もあります。積極性をアピールしようと無理にNGな質問をすると、かえって採用担当者にマイナスの印象を与えかねません。
質問内容を考えるときは、同時に会社説明会ではNGとされる質問も把握しておきましょう。NGな質問に共通する特徴は、3つあげられます。
会社説明会で聞かなくとも、少し調べれば容易にわかるような質問は避けるべきです。例えば事業内容や勤務地、福利厚生、前年度売上など基本的な企業情報は、コーポレートサイトや求人サイトなど、さまざまな場所で常時公開されています。
いつでも誰でも確認できる基本情報を会社説明会で質問しても、事前準備を怠っているとマイナスな印象を与えます。やる気がない、志望度が低いと思われかねません。会社説明会へ臨む前に、企業が運営している各サイトやSNS、求人情報は読み込んでおきましょう。
仮に基本的な情報に関する質問をするとしても、公開されている情報を理解した上で聞くほうが好印象です。事前に調査した上で、内容を踏まえた具体的な質問をするのであれば、担当者も志望度の高い学生だと受け取ってくれます。
事前にOB・OG訪問で企業理解度を上げておくと、基本的な情報に関する質問でも、より踏み込んだ内容に仕上げられます。
会社説明会は複数の学生が同席しており、それぞれ質問をしています。他の学生がすでに質問した内容を繰り返さないように注意しましょう。質問の仕方が異なっていても、内容が同じであれば周囲の話を聞いていなかったと思われます。
会社説明会に参加している担当者も、ひとりの人間です。学生ゆえの失敗にはある程度慣れているものの、やる気が感じられない相手よりも、真面目に聞き入ってくれる学生のほうに好印象をもちます。
同じ内容の質問は、企業の担当者に無駄な時間を使わせるのみならず、他の学生が質問する機会を奪うおそれもあります。質問内容が被らないように、他の学生の質問や担当者からの回答にも耳を傾け、重複しないように配慮することが大切です。
他の学生が行った質問や担当者からの回答を聞いておくと、自分が気付かなかったポイントや、新しく聞きたいことが見つかる場合もあります。
企業や担当者が回答しにくい質問は避けたほうが無難です。具体的に例をあげると、NGな質問内容は下記の通りです。
・企業の内部事情に関すること
・企業のマイナスイメージにつながること
・従業員のプライベートに関すること
・現段階では明確な答えが出せないもの
など
企業の内部事情に関する質問は、例えば離職率や人事評価の詳細などがあげられます。就活生としては気になる部分ではあるものの、直接尋ねると失礼にあたる質問です。
どうしても聞きたい場合は、ポジティブな言い回しで質問しましょう。離職率は定着率と言い換えられます。
不祥事など企業のマイナスイメージにつながる質問も、言い回しを工夫することが大切です。「〇〇の件では、御社の対応が素晴らしいと感じました。その後のイメージアップ戦略について…」と、前向きな聞き方をすると、担当者も答えてくれる可能性があります。
従業員の休日や昼休みの過ごし方などプライベートなことを聞いたり、配属先や転勤の有無など現段階では回答しかねることを聞いたりすることも避けましょう。
企業が答えにくい質問は、就活サイトや口コミサイトで事前にリサーチしておくことが失敗を避けるコツです。
会社説明会は、コーポレートサイトやSNSでは探れないような内容まで、企業の情報を得られる場です。また、受動的に説明を聞くのみならず、積極的に質問したり洗練されたマナーで振舞ったりすることで、採用担当者の印象に残りやすくなります。
この記事で解説した質問例を参考に、気になる企業の会社説明会でしっかりと爪痕を残しましょう。