

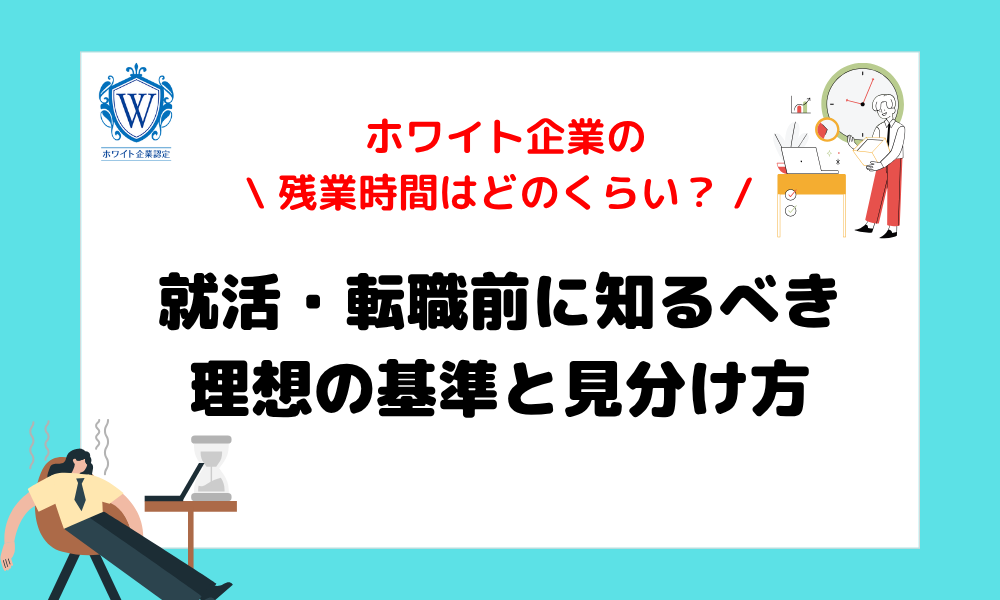
2025年10月28日に更新済み
求人票に「残業月20時間以内」と書かれていると、思わず安心してしまいますよね。
でも実際のところ、「20時間以内ならホワイト」「それ以上ならブラック」と言い切れるのでしょうか?
残業時間は、働きやすさを知るための大切な目安ではありますが、短ければホワイト・長ければブラックという単純な話ではありません。
この記事では、ホワイト企業の残業時間の実態と、数字の裏にある「働き方の質」に注目しながら、あなたに合った企業を見極めるヒントを紹介します。
目次
残業時間とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)や、企業が定めた所定時間を超えて働いた時間のことです。
企業によっては1日7時間勤務などの制度もあり、その場合は7時間を超えた時点で残業となります。
ホワイト企業では、こうした残業時間の把握と支払いを正確に行い、働く人の健康を守る仕組みが整っています。
2019年の働き方改革関連法により、企業の残業時間には以下の上限が定められました。
【原則】
月45時間以内/年360時間以内
【特別な事情がある場合でも】
年720時間以内・複数月平均80時間以内・単月100時間未満が上限
多くのホワイト企業では、この法令を遵守したうえで、「月20時間以内」などの社内基準を設定し、より健全な働き方を目指しています。
残業代(時間外労働の割増賃金)は、労働基準法で定められたすべての企業に共通する義務です。
ホワイト企業であるかどうかに関係なく、労働者が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合には、企業は必ず割増賃金を支払わなければなりません。
法的な根拠(労働基準法第37条)
法定労働時間を超えて働かせた場合、以下の割増率で残業代を支払う義務があります。

一般的に「月20時間以内」は、心身の負担が少なく、プライベートとの両立がしやすい水準とされています。
ただし、20時間を超えたからといってホワイトではない、というわけではありません。
繁忙期には一時的に残業が増えることもありますが、その分しっかり休める制度があったり、業務分担が整っていたりすれば、十分に健全な働き方といえます。
重要なのは、「時間の長さ」ではなく、“その時間をどうコントロールできているか”という点です。
業界や職種によっても差があり、「自分の志望業界ではどの程度が平均なのか」を把握しておくと安心です。
金融・通信業界
平均20時間前後
製造業
15〜25時間前後。生産計画の見直しで短縮が進行中
建設・広告業
以前は長時間労働が課題でしたが、現在は月30時間未満の企業も増加
ホワイト企業では、繁忙期でも残業時間が急増しないよう、人員配置やタスク分散で年間のバランスを保っています。
また、繁忙期に働いた分を閑散期にきちんと休む仕組みが整備されているなど、「一時的な負荷」と「年間の健全さ」を両立しています。
■不要な会議や資料作成の削減
■RPA・AIによる定型業務の自動化
■チャットやクラウドによるスムーズな情報共有
ホワイト企業では、「残業を減らすこと」よりも、『時間の使い方を最適化すること』に重点を置いています。
ただ「残業を減らす」ではなく、「限られた時間で成果を出す」働き方が重視されます。
ホワイト企業では、適切な人員配置により、特定の個人に業務が集中しない仕組みが整っています。チーム全体で業務を分担し、互いにサポートし合う体制が構築されています。
また、繁忙期には応援体制を組んだり、外部リソースを活用したりすることで、従業員の負担を適切に管理しています。
新人や異動者に対する教育体制も充実しており、早期に戦力化することで、既存メンバーの負担軽減にもつながっています。
有給休暇も取得しやすく、「休んでも回る組織」を実現しています。
■定時退社を推奨
■ノー残業デーの実施
■上司が率先して早く帰る
■PC自動シャットダウンの導入
残業時間が少ないホワイト企業の多くは、「長く働く=頑張っている」ではなく、「時間を上手に使う=プロフェッショナル」という価値観を大事にしています。

ホワイト企業認定企業の中には、業界特性や繁忙期によって月20時間を超えるケースもあります。
しかし、そうした企業でも共通しているのは、『社員が納得感を持って働ける環境づくり』に本気で取り組んでいるという点です。
重要なのは、残業時間という“数字”そのものではありません。
短い時間で高い成果を生み出すための仕組みを整え、社員の生産性と納得感を両立できる組織づくりに挑戦している企業こそ、真にホワイトと言えるでしょう。
就職・転職活動の中では、残業時間という表面的な数値だけでなく、その背景にある企業の考え方や取り組み姿勢にも目を向けてみてください!
求人票で確認したいのは、
「平均残業時間が具体的に数値で示されているか」。
「残業少なめ」などの曖昧な表現よりも、「月平均15時間」などの明示がある方が透明性が高いです。
また、数字が全社平均なのか、特定部署の平均なのかも確認が必要です。
営業・事務・開発など、部門によって大きく異なる場合もあるため、自分が応募するポジションの実態を把握することが重要です。
「固定残業代」「みなし残業制」を導入している企業では、超過分の支払いルールが明確にされているかも要チェックです。みなし残業を超える残業をした場合、追加で残業代が支払われることが明記されているか確認しておきましょう。
面接で残業時間について質問することは全く問題ありません。
むしろ、働き方を真剣に考えている証拠として、前向きに評価される場合も多くあります。ただし、質問の仕方によっては、相手に与える印象が大きく変わります。
✕ ストレートすぎる聞き方は避ける
「残業時間はどのくらいですか?」
このように直接的に尋ねると、「残業をしたくない人」という印象を持たれる可能性があります。悪意がなくても、防御的な印象を与えてしまうことがあるため、聞き方を工夫することが大切です。
✅ 好印象を与える質問の仕方
≪ ① 企業理解を深める姿勢を見せる ≫
「御社での働き方についてもう少し具体的にお伺いしたいです。
1日の流れや、繁忙期とそうでない時期で働き方にどのような違いがあるか教えていただけますか?。」
このように質問すると、「自分の業務を具体的にイメージしようとしている」と受け取られ、前向きで主体的な印象を与えます。
✅ 好印象を与える質問の仕方
≪ ② 長期的に働く意欲を前置きする ≫
「長く活躍できる職場を探しているので、働き方や生産性向上の工夫についてもお伺いしたいです。御社では業務効率化や残業削減にどのように取り組まれていますか?」
このような前置きを入れることで、 “条件確認”ではなく“働き方への理解”として伝わり、企業選びを真剣に行っている姿勢を示すことができます。
💡 質問のコツまとめ
■「残業の有無」ではなく、「働き方全体」をテーマに聞く
■前置きで「長く働く意欲」を伝えると誠実な印象に
このように、聞き方を少し変えるだけで、
「残業を避けたい人」ではなく「自分に合う働き方を見極めている人」というポジティブな印象を与えることができます。
最近では多くの企業が業務のDX・デジタル化に取り組んでいます。
■DX・デジタル化による業務効率化
■業務プロセスの見直し(会議短縮・標準化)
■勤怠管理システムでの労働時間の可視化
こうした取り組みの目的は、“残業時間を減らすこと”ではなく、「社員が最大限力を発揮できる環境をつくること」にあります。
残業時間は、企業の働き方を映す鏡のひとつです。
多くのホワイト企業が月20時間前後を目安にしていますが、数字だけで良し悪しを判断することはできません。
重要なのは、
■残業が発生する「理由」
■コントロールのしやすさ
■休暇取得とのバランス
■組織としての支援体制
これらを総合的に見て、「自分に合った働き方ができるか」を見極めることが大切です!