

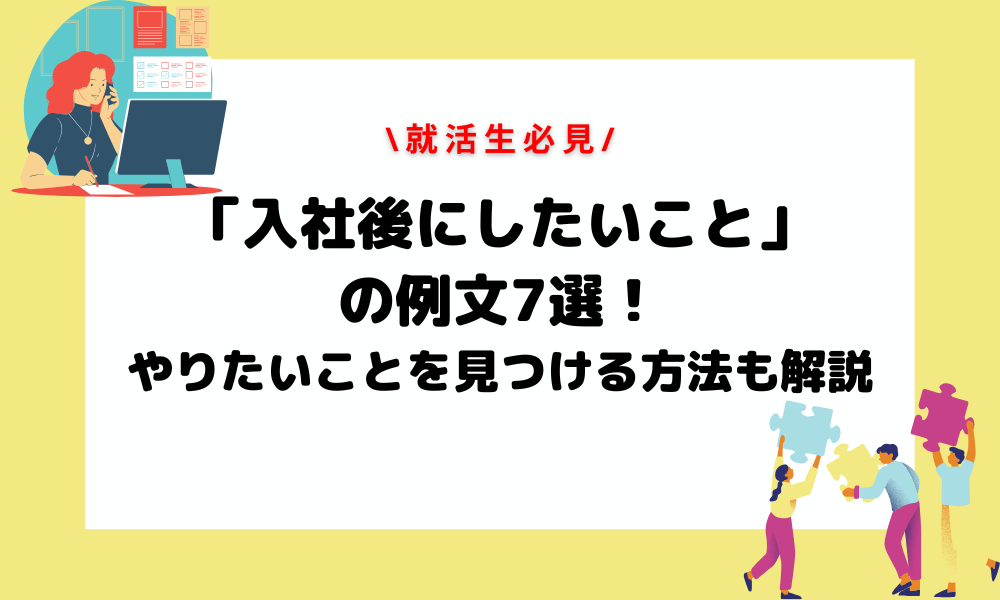
就活中、「入社後に挑戦したいこと/やりたいこと」を聞かれるシーンがあります。
入社後にしたいことを「思いつかない」「面接やエントリーシートでどう答えたら良いか分からない」など、悩みを抱えている学生も多いかと思います。
また、なぜ入社後にしたいことを質問されるのかも気になりますよね。
「入社後にしたいこと」は、質問される意図を理解したうえで、伝わりやすい内容を準備すれば十分対策できる質問です。これまでの就職活動や、過去の経験を振り返り、自分が興味のあること、得意なことなど、振り返ってみましょう。
この記事では「入社後にしたいこと」を聞かれる理由や、上手く伝える方法を解説しますので、是非参考にしてください。
目次

エントリーシート(ES)や面接で「入社後にしたいこと」を聞かれるのは、おもに以下3つの理由があるからです。
1.学生のキャリア観・ビジョンを知るため
2.事業内容や企業理念の理解度を確かめるため
3.働くイメージが湧いているか確かめるため
1つ目は、学生のキャリア観やビジョンを知るためです。
企業が「入社後にしたいこと」を聞くのは、「学生の将来像を実現できる環境が自社にあるか」確認し、採用のミスマッチを防ぐ意味合いが強いです。
企業は、採用した学生には目指すキャリアを実現してもらいつつ、自社で長期的に活躍してほしいと思っています。そのため、「どのようなキャリアを重ねたいのか、どうなりたいかのビジョンを、自社で叶えられるか」が気になっています。
そのため、「この人のやりたいことは、うちの会社では実現させてあげられなそうだ」と感じると、ミスマッチな人材と判断される可能性があります。
企業にとって避けたいのは、入社後に目指すキャリアが実現できないことが分かり、早期退職されてしまうことです。選考の段階で入社後にしたいことを聞くことで、将来的にどれくらい自社で活躍してくれそうかを見ています。

2つ目の理由は、学生が自社の事業内容や、企業理念を理解しているのか確認するためです。
事業や理念を正しく理解できていないと、事業に興味が持てなくてやめてしまったり、目標に向かっているチームの士気を下げたりしてしまうリスクがあります。
一方で、事業内容や企業理念に心から興味を持っている学生は、その方自身が活躍するだけでなく、組織にも良い影響を与えてくれることが期待できます。そのため、採用担当は、「入社後にしたいこと」を質問することで、事業内容や企業理念の理解の深さを確認しようとするのです。
3つ目の理由は、実際に自社で働くイメージが具体的に湧いているのかを確認するためです。
エントリーシートや面接の時点で「入社後にしたいこと」を具体的に答えられるのは、入社前からその企業で働くイメージが湧いているからです。
働くイメージを適切に持てていれば、入社後に業務が合わなくて早期離職してしまう、という事態も避けやすいです。もしイメージがずれていた場合は、選考の中で正しい情報を伝えることができるので、企業側は「入社後にしたいこと」の質問を介して、学生に仕事への理解度を深めてもらいたいと考えています。
また、学生がどんな働くイメージを持っているかは、入社後の配属先を決めるうえでも重要な判断材料になることです。

目標を突然聞かれても、スムーズに答えられる人は少ないでしょう。ここでは、「入社後にしたいこと」の見つけ方を解説します。
やりたいことが見つからないときは、反対にやりたくないことから考えましょう。消去法で考えると、何ならできるのか、何ならしても良いと思えるのかが分かります。
・チームプレーしたくない
・1日中座り仕事は嫌だ
・残業はなるべくしたくない
・BtoBの仕事は避けたい
やりたくないことは、入社後にストレスの要因となるおそれがあるため、消去法で考えることで、入社後のミスマッチを防げます。
長く続けられる仕事を見つけるためにも、効果的な方法です。
自分はどのような人間か、価値観や性格から分析しましょう。客観的に整理しておくと、自分の性質に合った目標を立てられ、将来的にはモチベーションアップが期待できます。
好きなことを優先して目標を立てると、現実とのギャップが生じたときに心が折れやすくなります。仕事を続ける気力がなくなる場合もあるため、価値観や性格も考慮した目標探しが必要です。
自分の価値観や性格を分析するための質問例は、以下の通りです。
【質問例】
・課題ができたとき、どのような行動で解決を目指したのか
・グループ活動をするときの役回りは?
・モチベーションが下がるときの原因は何か
・モチベーションアップにつながる理由は何か
モチベーショングラフを使った自己分析もおすすめです。モチベーショングラフとは、幼少期から現在に至るまでのモチベーションを折れ線グラフにするフレームワークです。縦軸がモチベーション、横軸が時間の流れを表します。
グラフを活用して、どのようなイベントがモチベーションの上下に影響したのか、原因とともに考えましょう。下がった後はどのような理由で上がったのかも考えると、困難の乗り越え方に気付けます。
社会人になると、苦手な業務を任されることもあります。過去の苦労した体験を棚卸しておくと、自分がやりたいことに取り組むとき、どのような障害のリスクがあるか分かります。苦労した体験を乗り越えたときの手法や思考が、業務にも活かせるかもしれません。
・レポートがいつも再提出になっていたが、何度も修正してまとめる能力が身に付いた
・プレゼンテーションが苦手だったが、仲間に練習に付き合ってもらって成功した
このように、苦労した経験を棚卸しするときは、解決方法も思い出しましょう。例えば2つの例は、どちらも修正や練習をめげずに繰り返したことで結果につながっており、地道な努力ができることを表しています。
WILL・CAN・MUSTの3つの輪を活用したフレームワークで、思考を整理しましょう。それぞれ以下の意味をもっています。
WILL(現在の自分がやりたいこと):今の自分が描く将来像のこと
CAN(現在の自分ができること):今の自分のスキルでできること
MUST(現在の自分がやらなければならないこと):優先的に取り組むべき課題のこと
3つのグループに分けて、自分がやりたいことやるべきことを整理します。
CANは強みであり、MUSTは使命でもあります。CANとMUSTに共通する部分がある場合、現在の自分ができること・やらなくてはならないことが適職です。
WILL・CAN・MUSTの3つの輪が重なり合うところが、高い満足度を得られる仕事です。自分にできることを活かして、自分がやりたいこと・やるべきことに取り組める状態であり、モチベーションにもつながります。
適職に沿った「入社後やりたいこと」が答えられる学生は、採用担当者から客観的に自分を理解できていると評価してもらえます。
自分の理想像から逆算して考えると、やりたいこと・今やるべきことが段階ごとに明確化できます。
以下の要領で、理想像から現在までのステップを逆算してみましょう。
【質問例】
・将来どんな仕事をしていたいか
・〇年後はどんな役職についていたいのか
・〇年後は年収いくらに達していたいのか
例えば3年・5年・10年後のビジョンを描いて、到達するためにはどのような経験や学びが必要なのか、何をするべきか考えると、ゴールまでの道筋が見えてきます。

「入社後にしたいこと」をうまく伝えるためのポイントは大きく2つあります。
1.自分の経験や価値観と、入社後のビジョンを紐付ける
2.企業や業界を深く理解していることを伝える
ここでは、具体的な伝え方と、内容に盛り込むべきポイントをお伝えします。
1.まずは結論から伝える
最初に「入社後にしたいこと」を一言で簡潔にわかりやすく伝えます。
【例】
私は社会のニーズにマッチした商品開発したいです。
2.具体的な業務や事業内容を伝える
具体的にどのような仕事をしたいのか、最初に伝えた「入社後にしたいこと」に肉付けしていきます。
【例】
御社の〇〇商品に感銘を受け、私も社会にニーズがある商品開発に携わりたいと考えるようになりました。実際に商品開発部の〜〜さんに商品開発の一連の流れを聞いて、商品開発のなかでもユーザーに近い市場調査やユーザーインタビューの業務に携わりたいと考えています。
3.自分の経験や価値観をどう活かすか伝える
自分の経験や価値観をどう活かすかを1〜2に紐付けて伝えます。
【経験や価値観の例1】
商品開発の経験はありませんが、〇〇業界で長くアルバイトをして新商品に多く触れてきました。新商品でお客様が困っていたことを解決し笑顔にできる喜びを忘れることはありません。
【経験や価値観の例2】
私は、困っている人のそばに寄り添える人間でありたいと考えています。サークルで問題が起きたときも、全員の意見をよく聞くことを大切にして活動してきました。
【入社後にしたいことの例】
入社後は商品開発のノウハウや技術を学びながら、社会のニーズにマッチした商品開発したいです。
「入社後にしたいこと」を話す際には、今までの経験や価値観と入社後ビジョンを紐付けて、なるべく具体的に伝えるのがポイントです。
自分が入社後にどのような仕事や事業に関わりたいのかを伝え、なぜその考えに至ったのか根拠となる理由を伝えていきます。具体的な経験にエピソードを加えたり、自分の性格や強みなどを盛り込んだりするのもポイントです。
ただやりたいことを伝えるのではなく、過去・現在から進みたい未来を結んだときに、結んだ線のうえこの仕事があることが伝わると、納得感のある内容になります。
企業や業界を深く理解していることを伝えるのもポイントです。
「入社後にしたいこと」を具体的に伝えるには、企業や業界のことを深く理解する必要があります。
事業内容やサービス内容、現場配属時の業務イメージなど、自社を理解していない学生を企業は積極的に採用したいとは考えません。そう考えると企業や業界研究していることが、入社後にしたいことを通じて伝われば良いイメージを与えられます。
例えば、業界内の同業他社との違いを盛り込みつつ「入社後にしたいこと」に答えれば、内容に信憑性が加わり、より伝わりやすくなるでしょう。
ここでは、「入社後にしたいこと」を伝えるとき、どのような点に注意するべきかNGポイントをもとに解説します。
「入社後にしたいこと」は、仕事と関係のある内容にしましょう。以下のように関係がない目標は、適切とはいえません。
・大人向け商品の会社で「子ども用品に力を入れたい」
・ブライダル事業の会社で「カフェ部門を作りたい」
・IT企業で「環境保護で地域貢献したい」
企業は、業績に貢献できる人材を入社させたいと思っています。実際の業務内容と関係の薄い目標は、入社後の活躍イメージしにくくなります。場合によっては「本当に企業研究してきたのか」と疑われかねません。
事業内容と絡めつつ、自分なりの目標を立てることが大切です。
目標値を具体的に設定するときは、以下のようにゴールが低くならないように注意しましょう。
・ビジネスマナーを身に付ける
・プロジェクトに参加する
・入社3年で自分の企画を通す
企業が求めている人材は、長期的に貢献してくれるタイプです。目の前の短期的に叶う目標ではなく、長期スパンをイメージして目標を立てる必要があります。
反対に、目標が高すぎて非現実的になっている場合も、ネガティブな印象を与えます。
志望度の高さをアピールするためには、応募企業でなければ実現できない目標を伝えることが大切です。以下のように他社でも目指せる内容は、志望度が低いのではと誤解されます。
・インターネット広告で成果を出せるようになりたい
・営業のプロになりたい
・プログラミングのスキルを磨きたい
志望度の高さを出すコツは、応募企業の事業内容と絡めた内容にすることです。応募企業が注力したり独自開発したりしている事業・分野にフォーカスした内容で伝えると、熱心に企業研究したこともアピールできます。
質問は、会社でやりたいことについて聞いています。以下のように個人的な目標に偏った内容は、マイナスの評価につながります。
・御社で経験を積んで独立開業したい
・御社の〇〇が好きだからもっと知りたい
・将来は〇〇ができるようになりたい
採用担当者が知りたいのは、自社にどのように貢献してくれるかです。個人的な夢や目標だけでは、採用するメリットを感じてもらえません。
業務や職種に活かせる目標を立て、企業に貢献する姿勢を見せることが大切です。
努力への前向きな姿勢や、謙虚さを見せようとして、無意識にネガティブな表現を用いていないでしょうか。
・現時点ではまったく知識がありませんが
・学生時代は人と話すのが苦手だったのですが
・少しずつ学ばせていただければ
これから頑張りますと伝えているつもりでも、担当者には後ろ向きな印象を与えるおそれがあります。「業界について少しも勉強してこなかったのか」「苦手なのに来たのか」と、受け取られかねません。
謙虚な姿勢は美徳とされている日本でも、度が過ぎれば悪い印象につながります。「入社後にしたいこと」はあくまで目標に対する質問なので、回答も前向きで希望にあふれた内容を心がけましょう。

業種によって、求める人物像は異なります。業種に合わせて「入社後にしたいこと」の内容を変えて、採用担当者に自社と相性の良い人材であることをアピールしましょう。
【例】
私は、多様化している現代のライフスタイルに対応できる商品の企画をしたいです。御社はお客様のライフスタイルに合わせて、幅広い返済方法に対応していらっしゃいます。お金の借り方もより多様化させて、お客様がより気軽にサービスをご検討いただけるようにしたいと考えております。
私は学生時代、ボランティアで地域のさまざまな立場の方から悩みを聞き、最適な行政支援を提案する活動を行っておりました。活動時に培ったヒアリング能力や学んだことを活かして、新たな金融サービスづくりに携わりたいです。
【例】
入社後は、大人の女性が気軽に持ち歩ける可愛いコスメシリーズの開発に挑戦したいと考えております。御社の主力商品は手ごろな価格と可愛らしいデザインで、若い女性を中心に高い人気があります。先日の会社説明会では、40代以上の女性にも品質の高さで注目を集めているものの、若いデザインがマッチしにくいことをお話されていました。
私の母も、御社の〇〇シリーズの使いやすさが好きで、よく私の愛用品を貸してほしいと言ってきます。私が入社したら、若者向けのエネルギッシュな可愛さではなく、大人の女性が気軽に持ち運べる上品な可愛らしさをデザインに盛り込んだシリーズで、御社の新たな販路作りに貢献したいと考えています。
【例】
私は入社後、営業職として国内水産業と御社の共同事業に貢献したいです。
私の実家は漁師であり、私も中学生のころから兄とともに家業を手伝っております。家業を通して、漁師たちならではのコミュニケーションの流儀を学び、現場の課題も体感しました。また、船上では一瞬の判断ミスが命取りとなったり、獲物を劣化させたりするリスクがあるため、誰もが自主的に動かなくてはなりませんでした。
家業で身に付けた水産業者の考え方や知識を活かして、現場の要望に応えつつサポートできる商社マンとして、新たな商品開発につなげたいと思っております。
【例】
私は入社後、女性やお子様のいるご家庭が安心して住める物件の提供をしたいと思っています。
私は大学へ進学するとき、上京に伴い御社の〇〇支店にて物件探しをしました。当時は家賃と駅からの距離しか重視していなかった私に対して、担当者の方が「ここは街頭が少ない地域だから、避けたほうが良いよ」など、快適に生活するためにチェックするべきポイントを丁寧に教えてくださいました。
私も入社後は書類上の情報のみならず、女性やお子様が安心して通勤通学したり、快適に暮らしたりするためには何を重視するべきかをお客様に伝え、長く住める物件との縁を提供したいです。
入社後にしたいことを伝えるときは、志望している職種との関連性も考慮しましょう。関係のない内容は、採用担当者に「本当は職種に興味がないのでは」と疑問を与えるおそれがあります。
ここでは、職種別に入社後にしたいことの例文を紹介します。
【例】
入社後は、お客様からご指名いただけるほど信頼できる営業職を目指したいです。
私は学生時代、テーマパークにて案内スタッフとしてアルバイトをしておりました。日本語の通じない外国人のお客様や幼いお子様と接することも多く、笑顔を崩さず、言語に表せられない要望を汲み取って対応する毎日は、非常にやりがいがありました。
御社の営業職はルート営業が中心と伺いました。営業職に配属されたら、アルバイトで培ってきたコミュニケーション能力や、相手の気持ちに真摯に向き合って潜在ニーズを探る力を活かして、「まず〇〇社さんに相談したい」とお客様にご指名いただけるチーム作りをしたいと考えております。
【例】
私は入社後、事務職として縁の下の力持ちを目指したいと考えております。私は学生時代、陸上部のマネージャーをしておりました。
大学入学から一人暮らしのチームメイトも多く、記録を伸ばすためには練習フォームのみならず生活面の改善も必要と考えました。日常生活や食事で気を付けるべきポイントなどを一人ひとりの特徴に合わせてノートにまとめ、ともに記録更新を実現してきました。
学生時代のマネージャー経験で培った、一人ひとりに合わせた資料の作り方や、効率化を考えてまとめる能力を活かし、メンバーや案件ごとに合わせたサポートでチームに貢献したいと思っております。
【例】
入社後は、SEとして幅広いリテラシーレベルに合ったソフトウェア開発を行いたいと考えております。
私は、中学校時代から趣味でオリジナルのソフト開発を行っております。部活やサークルの仲間に使ってもらったり、家族間で使ったりしているうちに、年齢層やライフステージごとのリテラシーレベルの違いがソフトの使い勝手に大きく影響することを学びました。
この経験や学びを生かし、幅広い立場のお客様に「使いやすい」「操作を覚えやすい」と思っていただける親しみやすいソフト開発をしたいです。
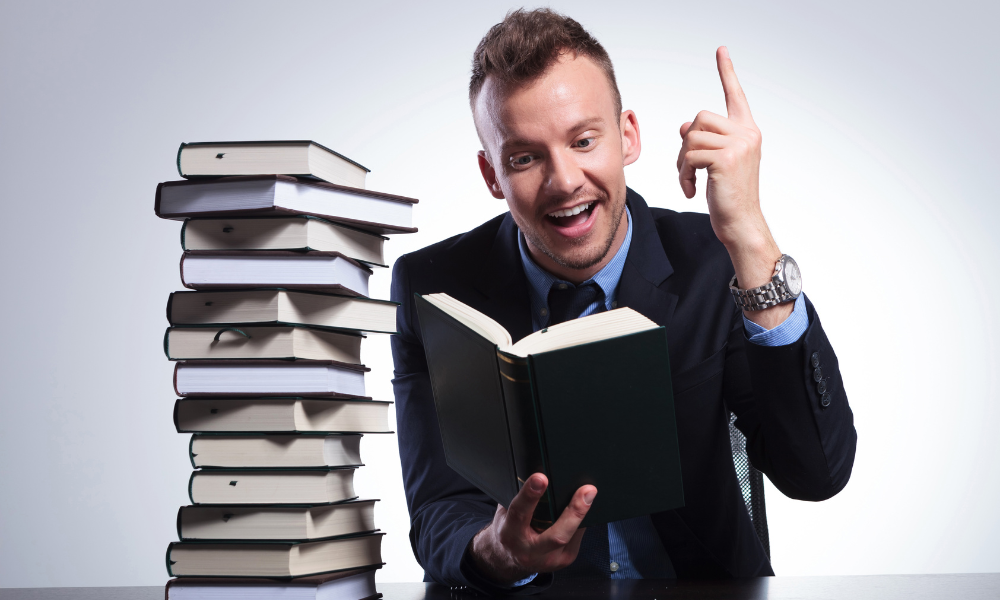
以上、入社後にしたいことを聞かれる理由や伝え方を、一部をご紹介しました。
「入社後にしたいこと」が聞かれる理由は以下を確認するためです。
1.学生の描く将来像と自社がマッチしているのか
2.事業内容や企業の経営方針について理解してもらえているか
3.具体的に働くイメージができているのか
「入社後にしたいこと」をうまく伝えるポイントは以下です。
1.自分の経験や価値観と、入社後のビジョンを紐付ける
2.企業や業界を深く理解していることを伝える
あなたが描く理想のキャリアを実現できる会社と出会うためにも、入社後にしたいことのイメージを膨らませてみてください!
入社前の状況で、入社後に何をしたいのか答えるのは難しいですがこの質問の回答内容によっては企業側は「自社に興味を持って、色々と調べてくれたんだな」と感じられるはずです。
正解はないので、あくまでも自分で企業理解を行い、そのうえで自分が何をしたいのかを考えるきっかけとして、捉えてみることをおすすめいたします。
皆さんの就職活動が、納得のいく方で進まれることを願っております。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。