

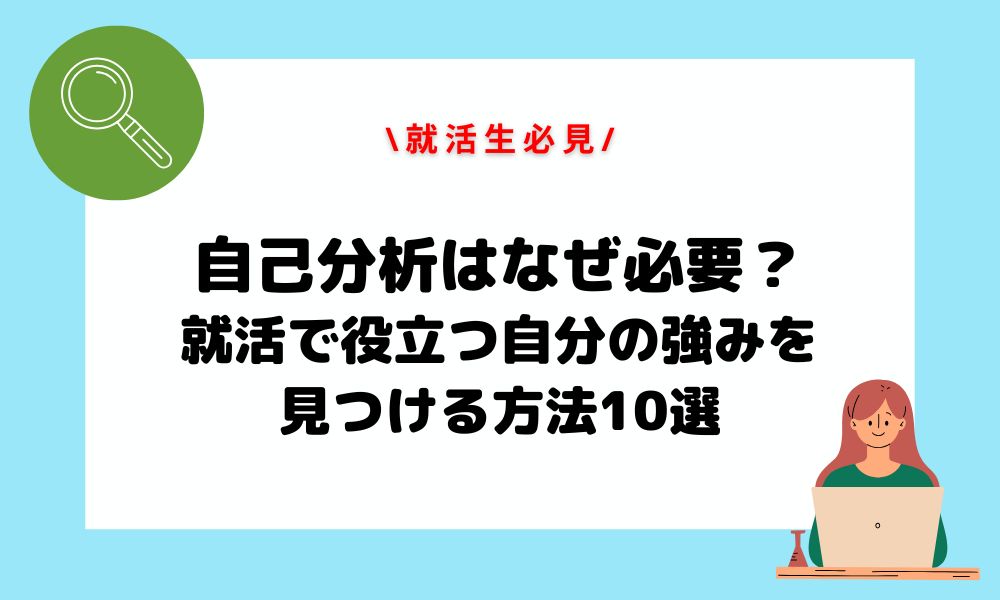
自己分析は就活中によく聞く言葉です。
では、就活ではどうして自己分析が必要なのでしょうか。
自己分析をしておくと、企業選びで迷いにくくなり、自己PRや志望動機も作りやすくなります。結果として、面接で話す内容に一貫性が出て、伝わり方が変わります。
退職理由をランキングにしたとき、仕事が(会社が)自分に合わなかったという理由は高い確率でランクインしています。
皆さんも就職活動を進める中で、
自分に合う仕事を見つけましょう
自分に合う会社の見つけ方
といったワードを目にする機会があったのではないでしょうか。
自分に合った仕事と出会い、納得のいく就職活動にするためにはしっかりとした自己分析が必要となってきます。
今回は、就活の礎ともいえる自己分析について、詳しく解説します。

自己分析とは、自分の性格や価値観、得意なこと・苦手なことを振り返って整理する作業です。これまでの経験を見つめ直すことで、自分は何を大切にしているのか、どんなときに力を発揮できるのかが見えてきます。
就職活動では、こうした自己理解が企業選びや面接での自己PRに直結するため欠かせません。

自己分析には、なぜそれを行うのかという明確な目的があります。ただ何となく自己理解を深めるのではなく、目的を意識することで、分析の質も深まります。ここでは、就職活動における自己分析の代表的な3つの目的を紹介します。
自己分析は、自分の考え方や行動の傾向、得意・不得意を把握するために行います。企業に自分を知ってもらうには、自分自身がどんな人間で、どのような価値観を持ち、どのような場面で力を発揮するのかを言語化する必要があります。
こうした自己理解が深まることで、自分に合う仕事や環境を見極めやすくなります。
過去の経験を整理し、どのような背景や意図で行動したのかを振り返ることで、自己PRや志望動機に具体性と説得力が生まれます。
どんな経験をして、何を学び、どう成長したかが言葉にできれば、採用担当者にも自分の魅力が伝わりやすくなります。自己分析は、その土台をつくる作業ともいえるでしょう。
自分が将来どんな仕事をしたいのか、どのような働き方を望んでいるのかを考えるには、自分の価値観や興味を明確にすることが欠かせません。
自己分析を通じて、自分が大切にしたい軸や方向性が見えてくることで、キャリアの選択に迷いが生じにくくなります。そのため、納得のいく進路選択をするための指針を立てやすくなるでしょう。


自己分析は、就職活動が本格的に始まる前に済ませておくのが理想です。多くの企業が採用活動を本格化させる大学3年生の3月ごろまでには、ある程度の自己理解を深めておくことが望ましいでしょう。
とはいえ、自己分析は一度やって終わりというものではありません。エントリーシートの作成や面接対策が始まるタイミングで、改めて自分の考えを整理し直すことも大切です。選考が進む中で気づく新たな視点や気持ちの変化を取り入れながら、必要に応じて自己分析をアップデートしていくことで、就職活動の精度が高まります。

就職活動において、自分自身の強みや価値観を把握しておくことが重要です。とはいえ、自分のことは自分が一番良くわかっていると思っていても、いざ言語化しようとすると意外と難しいものです。そこで役立つのが、目的や特性に応じたさまざまな自己分析の手法です。ここでは、誰でも取り組みやすく、かつ実践的に使える10の方法を紹介します。
自分史とは、これまでの人生を振り返り、経験や考えたことを時系列にして可視化する方法です。小学校から大学までの間に経験した印象的な出来事を洗い出し、その背景や自分の感情を深掘りすることで、自分の価値観や強み・弱みを客観的に見直すことができます。
手順としては、まず印象的だったエピソードをいくつかリストアップし、それぞれについて、なぜその出来事が印象に残っているのか、当時の感情や行動、学びや成長は何だったかを掘り下げていきます。
飾らず率直に記録することで、自分を良く知るヒントが得られ、志望動機や自己PRの素材にもなります。
ライフラインチャート(モチベーショングラフ)は、人生の出来事を横軸に、モチベーションの高低を縦軸にとって描くグラフ形式の分析手法です。
過去の体験に点数をつけ、その変化を線でつなぐことで、自分がどんなときに前向きになれるのか、何にストレスを感じやすいのかが視覚的に理解できます。
学生生活に特別な出来事がなかったと感じている方でも、自分なりの気づきや変化を再認識しやすい方法です。

学業・部活・アルバイト・趣味など、6つのカテゴリーにわたって印象に残っている体験を整理し、それぞれの場面で自分がどう行動したかを振り返ります。
どんな挑戦をしたのか、そのとき何を感じたのか、どんな結果が得られたかといった視点から、自分らしい行動特性を浮き彫りにします。
ポイントは、謙遜せず自分を前向きに評価することです。書き出した内容をもとに自分らしさとは何かを言語化することで、企業選びの軸や志望動機のヒントが得られます。
マインドマップは、中央に自分などのキーワードを置き、そこから連想される要素(得意なこと、価値観、経験など)を放射状に広げて整理する手法です。
視覚的に自分の思考を構造化できるため、アイデアを発想しやすくなり、自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の骨子づくりにも役立ちます。
キーワードごとに、なぜそう思うのかを問いながら深掘りしていくことで、自分の行動原理やモチベーションの源泉が明確になります。色分けや図解を取り入れると、記憶にも残りやすくなります。
WHYを掘り下げるという手法は、自分がこれまでの人生で選んできた行動や判断に対し、なぜそうしたのかと繰り返し問いかけていく自己分析法です。自分の価値観や行動原理が徐々に明確になり、最終的には志望動機や自己PRで語るべき本質にたどり着けるようになります。
まずは印象に残っている経験や、自分にとって大きな意味を持つ出来事をひとつ選びます。その出来事に対して、なぜそう思ったのか、なぜその行動を選んだのかと深掘りを続けていくことで、自分の内面にある一貫した価値観や動機が見えてくるはずです。
例えば、なぜそのアルバイトを続けられたのかという問いを出発点に、信頼されていたから、居心地が良かったから、意見をいえる環境だったからといった答えをたどっていくと、自分にとって働きやすい環境の特徴が明らかになります。
最初は当たり前に思える動機であっても、繰り返しなぜを問い続けることで、表面的な動機ではなく、深層にある自分の価値観にたどり着くことが可能です。

WILL・CAN・MUSTは、キャリアの方向性を整理するためにビジネスでも使われるフレームワークです。自己分析として活用する場合には、自分のやりたいこと(WILL)、今できること(CAN)、社会や企業から求められていること(MUST)を整理し、3つが重なる部分に理想の働き方や職種のヒントを見出します。
はじめに、自分の過去の経験やスキルから今できること(CAN)を具体的に書き出し、次に今後やりたいこと・挑戦したいこと(WILL)を思いつく限り挙げていきます。そして最後に、自分が興味のある業界や企業の求める人物像や役割を参考にしながら求められること(MUST)をまとめていきます。
それぞれを明確にしていく中で、CANは営業スキル、WILLは人を喜ばせること、MUSTは成果への責任といった重なりが生まれれば、顧客と信頼関係を築く法人営業職が自分に合った仕事のひとつとして浮かび上がってくるかもしれません。
WILLとCANが結びつかないと感じたときにも柔軟に考えることが大切です。
ジョハリの窓は、自分自身の性格や特性について、自己認識と他者認識のズレを可視化するためのフレームワークです。自己理解を深める上で、自分が知っている自分と他人が知っている自分を分類し、4つの領域(開放の窓、秘密の窓、盲点の窓、未知の窓)に分けて分析していきます。
分析を行う際は、まず自分で自分の性格や長所・短所を言葉にして書き出します。次に、家族や友人など信頼できる他者にも同じように自分に当てはまる特徴を挙げてもらい、それぞれを比較します。
その上で、両者が共通して挙げた項目は開放の窓、自分だけが認識していた項目は秘密の窓、他者だけが挙げた項目は盲点の窓、そしてどちらにもなかったものは未知の窓に分類します。
この分析によって、自分では気づかなかった強みや改善すべき盲点などを発見でき、自己PRにおいては開放の窓にある要素を自信を持ってアピールできるようになります。
また、意外な指摘をきっかけに新たな自己理解が進むという点でも効果的です。

MBTI診断は、アメリカで開発された性格タイプ診断のひとつで、93問の質問に回答することで、16タイプに分類される自分の性格傾向を明らかにする分析手法です。外向型(E)か内向型(I)か、直感型(N)か感覚型(S)かなど、自分では把握しきれなかった性格の側面を客観的に理解できる点が魅力です。
診断の流れは、制限時間(おおよそ12分)の中で設問に直感的に答え、診断結果として自分の性格タイプとその特徴、向いている業種や働き方の傾向などを確認するというものです。深く考えすぎず、自分の第一印象に従って回答することが、診断の正確性を高めるポイントとされています。
診断結果を活用すれば、チームで協働するのが向いている、論理的思考を活かせる仕事が合っているといった自己認識が深まり、企業選びや職種選定の方向性を具体化するのにも役立ちます。
他己分析は、自分以外の方から見たあなたの姿を知ることで、自己理解を客観的に深める方法です。自己分析は内省的な作業である一方、他己分析では家族や友人、先輩など信頼できる他者にヒアリングを行い、自分がどんな性格か、どんな仕事に向いていると思うかなどの質問を通して、自分では気づかなかった評価や印象を収集します。
その際、自分自身があらかじめ考えていた特性と、他人が挙げてくれた特性を見比べることで、共通していた点は自信を持つべき強み、食い違っていた点は新たな視点として捉えることができます。特に、自分では意識していなかった長所を他人から評価された場合、それは自己PRや面接の場で大きな武器になるでしょう。
この手法は、自己評価と他者評価のギャップを埋めるとともに、自分を客観的に見つめる姿勢を養う点でも有意義です。
最近では、多くの就活サービスが自己分析ツールを提供しており、これを活用することで手軽に自分の適性や強みを把握できます。質問に答えるだけで、価値観や能力、適職などを数値化してくれるツールもあり、データに基づく分析は主観に偏りがちな自己判断の補完にもなります。
まずは、各社が提供する自己分析ツールにアクセスし、診断を受けてみましょう。
さらに、自分だけでは方向性を見出しにくいときは、キャリアアドバイザーへの相談も効果的です。プロの視点からフィードバックを受けることで、就活の軸が明確になり、自己分析をより実践的に活かすことができます。

自己分析を効果的に活用するには、やり方だけでなく進め方にも注意が必要です。ここでは、自己分析を最大限に活かすために意識したいポイントについて解説します。
自己分析を始める前にまず意識したいのが、何のために行うのかという目的を明確にすることです。
面接対策のためなのか、志望企業を選ぶためなのか、あるいは自分の強みを見つけたいのかといった目的があいまいなまま進めると、情報を集めるだけで満足してしまい、分析結果を就活に活かせなくなるおそれがあります。
自己分析はあくまで手段であり、それ自体がゴールではないという意識を持つことが大切です。
自己分析では、自分を良く見せようとする気持ちを抑え、ありのままの自分と向き合う姿勢が求められます。
例えば、自分の弱みや過去の失敗にも正面から向き合うことで、本質的な価値観や成長のきっかけを発見できる可能性があります。
また、企業が求める人物像に自分を無理に当てはめようとするのは避けましょう。
自分を取り繕った分析は、面接時の発言に一貫性がなくなり、かえって信頼を損なうことにつながりかねません。
なんとなくこう思う、そんな気がするという漠然とした感覚で終わらせるのではなく、自分の考えや感情を具体的な言葉に置き換えることが、自己分析の精度向上につながります。
例えば、仲間と協力するのが好きという抽象的な表現ではなく、文化祭でリーダーとして全体をまとめる経験が楽しかったなど、事実に基づいたエピソードとセットで言語化することで、自己理解が深まり、他者にも伝わる形に仕上がります。
自己分析は一度行えば終わりではありません。人の考え方や価値観は、経験や環境の変化によって常に変わっていくものです。そのため、節目ごとに自己分析を見直し、アップデートしていく姿勢が求められます。
ただし、完璧な答えを求めていつまでも分析を続けるのは得策ではありません。ある程度のタイミングで、いったんまとめる、今の自分としての結論を出すという意識も大切です。
自己分析は手段であり、就活やキャリア選択に活かしてこそ意味があるのです。
就活サイトが提供する自己分析ツールやワークシートは、自己理解を深めるために役立ちます。しかし、表示された診断結果をすべて鵜呑みにするのではなく、自分自身の感覚や価値観と照らし合わせて判断することが重要です。
ツールはあくまで補助的なものであり、最終的な判断や解釈は自分自身に委ねられています。この診断は当てはまっているか、本当に自分はこう感じているのかといった問いを持ちながら活用することで、より信頼性の高い自己分析に仕上がります。

終身雇用時代は終わったと言われるようになりましたが、それでも安心して長く働き続ける会社に入りたいという方が大半ではないでしょうか。
就職活動の期間で、自分が働きたいと思える会社に出会い、そこへ就職し、自分の目標とするキャリア積み上げることができればそれに越したことはありません。
その第一歩として、しっかり自己分析をし、自分が大事にすべきポイントを明確にし、イメージを具体化していきましょう。
自己分析を通じて自分が大事としているポイントを把握すると、新たな気づきがあったりしますので、そんな発見を楽しみながら、ポジティブに就職活動を楽しめるとステキですね。